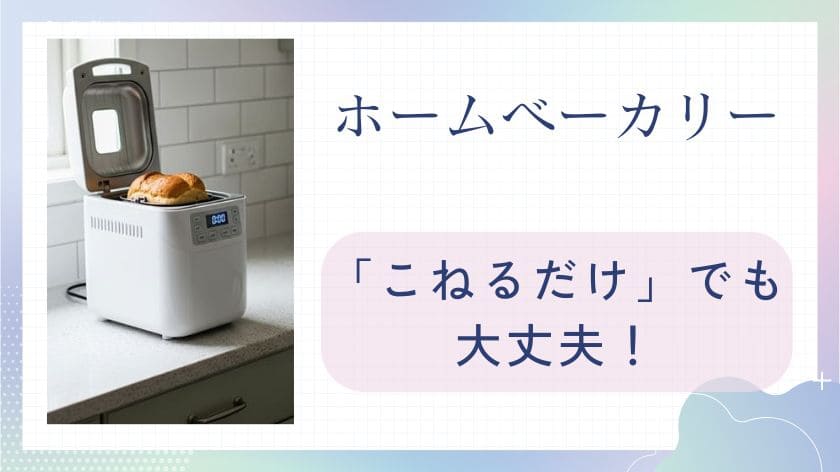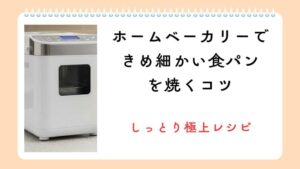「こねるだけでも大丈夫かな?」
「生地だけ作りたい!」
「本当に使いこなせるかな?」
ホームベーカリーの購入を惑われてる方に、ホームベーカリーは色々な使い方ができることを紹介しています。
実は、ホームベーカリーは「こねるだけ」「発酵するだけ」「焼くだけ」ということもできるんです。
この記事では、ホームベーカリーの「こねるだけ」機能に焦点を当てて、その具体的なやり方やレシピ、便利な機種について詳しく解説します。
この記事を読めば、こねるだけを使う方法や、こね時間、小麦粉の量、パナソニックやシロカ、アイリスオーヤマといった人気機種ごとの特徴がわかります。
さらに、パンニーダーとの違いやメリット・デメリットを比較したり、フードプロセッサーでも生地作りが可能であることにも触れます。
ホームベーカリーの使い方の可能性を知って、パン作りの幅を広げてみましょう。
- ホームベーカリーの「こねるだけ」を使う方法
- パン生地作りの失敗の原因と、成功させるコツ
- 主要メーカーの機種ごとの特徴や機能の違い
- ニーダーやフードプロセッサーとの比較
ホームベーカリーでも「こねるだけ」はできる?
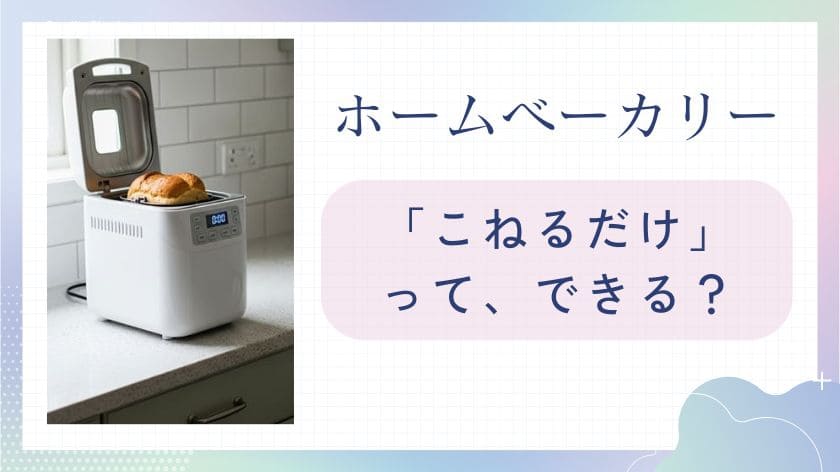
- 基本的なパンの作り方~時間配分
- その失敗、もしかして「こね不足」や「こねすぎ」が原因かも
- グルテン膜でこね上がりを確認しよう
- こねるだけの独立メニューとは?
- 「こねるだけ」を使ったグルテン膜チェックのやり方
- 生地だけ作る「生地コース」のやり方
- こねる時間はどれくらいがベスト?
- パンを作る時の小麦粉の量
- ミキシングのあとはどうすれば?
- パンづくりでいちばん大切なのがミキシング
基本的なパンの作り方~時間配分

パン作りは、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、基本的な工程はとてもシンプルです。
まずは全体の流れと、それぞれの工程にかかる時間の目安を掴むことから始めましょう。
パン作りの主な工程は、以下のようになります。
- 計量:材料を正確に測ります。
- ミキシング(こね):25分、材料を混ぜ合わせ、グルテンを形成させます。
- 一次発酵:60分、生地を休ませ、酵母の力で膨らませます。
- 分割・丸め:30分、生地をパンの数に分け、形を整えます。
- ベンチタイム:20分、生地を少し休ませ、成形しやすくします。
- 成形:10分、作りたいパンの形に整えます。
- 二次発酵(最終発酵):60分、成形した生地を再び膨らませます。
- 焼成:15分、オーブンで焼き上げます。
(時間はおおよそです)
時間配分はレシピや作るパンの種類、人、室温などによって大きく変わります。
一般的な菓子パンの場合、全体で3時間から4時間ほどかかることが多いです。
ホームベーカリーのオートメニューは、2番目の「ミキシング(こね)」から最後の「焼成」までの工程を自動で行ってくれます。
また、機種によって違いますが、こねるだけをしてくれたり、発酵だけ、焼成だけ、生地ができるまでなど、いろいろな機能があります。
その失敗、もしかして「こね不足」や「こねすぎ」が原因かも
なぜ、いろいろな機能がついているのかと言うと、もっとおいしいパンを手軽に作りたいという思いがあるからです。
というのも、「レシピ通りに作ったのに、パンがうまく膨らまない」「焼き上がりが固くなってしまった」といったパン作りの失敗は、多くの方が経験します。
その原因が「こね不足」「こねすぎ」になってる場合があるからです。
パン生地をこねる(ミキシングする)目的は、単に材料を混ぜ合わせるだけではありません。
小麦粉に含まれるたんぱく質に水分を加えてこねることで、「グルテン」という網目状の組織を作り出すことが最も重要です。
このグルテンが、イーストが発生させる炭酸ガスをしっかりと包み込むことで、パンはふっくらと膨らみます。
こねが足りないと、グルテンの膜が十分に形成されません。
すると、せっかく発生したガスが生地の外に逃げてしまい、ボリュームのない、目の詰まった固いパンになってしまうのです。
手ごねはもちろん、ホームベーカリーを使った場合でも、機種や粉の量によってはこね不足になることがあります。
逆に、こねすぎてしまうと、生地がだれてしまい、膜ははらなくなります。
なんども失敗を繰り返してしまうときは、一旦、オートメニューをやめて、手作りでパンを焼いてみれば、何がまずかったのがが分かるかもしれません。
とはいえ、こねるのはとても大変ですので、ホームベーカリーの「こねるだけ」の独立メニューがとても重宝します。
グルテン膜でこね上がりを確認しよう

何度やっても、ホームベーカリーでうまくおいしいパンができない場合、生地をチェックしてみましょう。
こねが終わって、発酵が始まる前に、生地を取り出して、しっかりとこね上がってるかどうかを見てみます。
そのための最も確実な方法が「グルテン膜のチェック」です。
これは、こね上がった生地の一部を両手で優しく、ゆっくりと引き伸ばしてみて、生地の状態を確認する作業です。
理想的なこね上がりの生地は、指が透けて見えるくらい薄い膜が、破れずにきれいに伸びます。
こんな感じです。

グルテン膜のチェック方法
- ホームベーカリーのこね工程が終了したら、生地を少量取り出します。
- 生地の表面が張るように優しく丸めます。
- 両手の指先を使って、生地を四方八方にゆっくりと引き伸ばします。
コネが不足していたりこねすぎていると、伸ばしている途中で、すぐにブツブツと切れてしまいます。
もしも、グルテン膜ができてなかったら、「こね」が問題になってる可能性があります。
オートメニューをとりあえずやめて、「こね」の独立メニューとか、マニュアルメニューで、生地づくりを試してみてください。
ただし、ホームベーカリーのオートメニューは、誰がやってもうまくいく設定になっています。
うまくいかない原因が、こね時間ではなくて、温度だったり、材料の入れ方の可能性もあります。
もう一度、取扱説明書を読んでみることもおすすめします。
こねるだけの独立メニューとは?
ホームベーカリーの最もシンプルな活用法が、こねる作業だけを機械に任せる使い方です。
多くのホームベーカリーには、「パン生地コース」とは別に、こねる工程だけを独立して行う「こねメニュー」があります。
「パン生地コース」は、こねから一次発酵までを行うにたいして、「こねメニュー」は、こねる工程だけを独立しておこないます。
最近の機種には、こね時間はもちろん、こねるスピードをを自分で設定できる機能が搭載されているものがあります。
もし、購入予定の機種に独立したこね機能がない場合は、「うどん・パスタコース」「そばコース」などで代用できることもあります。
これは、こねるだけのシンプルな動作をするコースだからです。
あなたがほしいと思われてる機種の取扱説明書「オートメニュー一覧」などで工程を確認してみてください。
「こねるだけ」を使ったグルテン膜チェックのやり方

ホームベーカリーには色々なメーカーがありますが、独立メニューの「こねるだけ」は、だいたい同じようなやりかたです。
材料を入れて、時間をセットして、スタートメニューを押すだけです。
では、こね機能をつかったグルテン膜チェックのやり方と、生地の作り方を紹介します。
- パンケースに、バターや油脂以外の材料を入れる。(水分を先に入れるか、粉を先に入れるかは機種の指示に従ってください)
- 「こね」や「うどん」コースなどをスタートさせ、5~10分ほどこねます。
- 生地がある程度まとまったら、室温に戻したバターや油脂を加えます。
- さらに10~15分ほどこねます。
- こねが終わったら、前述の「グルテン膜チェック」で生地の状態を確認します。
この方法なら、生地のこね上がりを最適な状態で見極めてから、自分の手で一次発酵に移ることができます。
温度管理なども自分で行えるため、パン作りの成功率がぐんと上がります。
こねたあとは、ホームベーカリーの発酵機能、焼成機能を使ってもいいですし、ご自身で発酵を管理してオーブンで焼いてもいいです。
生地だけ作る「生地コース」のやり方
「こねるだけ」と似ていますが、「生地だけ作る」という機能もあります。
機種によりますが、「パン生地コース」「生地コース」などという名前で、こねから一次発酵までを全自動で行えます。
この方法は、材料を入れたら一次発酵が終わるまで完全に機械任せにできるため、非常に手軽で、忙しい方や初心者の方にはとても便利な機能です。
一次発酵まで完了した生地を取り出して、分割、成形、二次発酵、焼成と進めていけば、様々なアレンジパンを作ることができます。
「パン生地コース」のメリットと注意点
メリット
- 材料を入れたらスイッチひとつで、一次発酵まで完了する手軽さ
- こねている間や発酵中に他の作業ができる
注意点
- こね上がりの状態(グルテン膜)を確認できないまま発酵に進んでしまう
- こね上げ時の生地温度が、季節や室温によって適切でない場合がある
手軽さは大きな魅力ですが、もし「パン生地コース」を使っていてパンがうまく膨らまないと感じる場合は、こね不足や発酵温度が原因かもしれません。
そのような場合は、一度「こねるだけ」の方法に切り替え、各工程を自分で管理してみることをおすすめします。
こねる時間はどれくらいがベスト?

ホームベーカリーでこねる時間は、一概に「何分が正解」とは言えません。
なぜなら、機種のモーターの強さ、一度にこねる粉の量、室温、そしてパンのレシピ(水分量や油脂の量)によって、最適なこね時間は変わってくるからです。
ただ、一般的な目安としては、多くのホームベーカリーで合計20分前後をこね時間の基準としていることが多いようです。
内訳としては、最初の5~10分でグルテンの骨格を作り、油脂を投入してからさらに10分ほどこねて、なめらかな生地に仕上げるイメージです。
大切なのは、時間の数字だけを見るのではなく、「グルテン膜」の状態で判断することです。
20分こねても膜が弱いようであれば、5分追加でこねてみる。
逆に、バターを多く使ったリッチな生地などは、少し長めの時間が必要になることもあります。
こね時間の調整のコツ
- こね不足を感じたら
5分単位で追加してこね、その都度グルテン膜をチェックする - 国産小麦を使う場合
吸水が少なくベタつきやすいことがあるため、様子を見ながら少し長めにこねると安定することがあります - 気温が高い夏場
こねる時の摩擦熱で生地温度が上がりすぎないよう、フタを開けてこねたり、冷水を使ったりする工夫が必要です。生地温度は25℃~28℃が理想とされています
パンを作る時の小麦粉の量
ホームベーカリーは「1斤用」「1.5斤用」といったように、作れるパンのサイズ(容量)が決められています。
1斤用のホームベーカリーの場合、付属のレシピブックでは強力粉250gが基準となっていることがほとんどです。
しかし、生地だけを作る場合、「もう少しだけ増やしたい」と思う場面はよくあります。
では、1斤用のホームベーカリーで、最大どれくらいの粉量までこねることができるのでしょうか。
小麦粉の投入量は機種のモーターのパワーに依存するため、一概には言えませんが、多くの取扱説明書を見ると、280gあたりが上限の目安と考えるのが良さそうです。
これ以上増やすと、モーターに過度な負荷がかかり、うまくこねられないだけでなく、故障の原因になる可能性が高まります。
くれぐれも、取扱説明書を良く読んで、上限値を調べてください。
ミキシングのあとはどうすれば?

ホームベーカリーで理想的なグルテン膜を持つ生地がこね上がったら、次の工程へ移ります。
- 一次発酵
- ガス抜き・分割・丸め
- ベンチタイム
- 成形
- 2次発酵
- 焼成
手動でオーブンなどを使う方法と、ホームベーカリーの独立メニューを使うやり方があります。
1. 一次発酵 ~生地を休ませ、大きく育てる~
ミキシング(こね)で形成されたグルテンの網目構造の中に、酵母(イースト)が作り出す炭酸ガスを溜め込み、生地全体をふっくらと膨らませる最初の発酵工程です。
まず、こね上がった生地をホームベーカリーのパンケースから取り出し、表面がなめらかになるように優しく丸め直します。
そして、薄くオイル(分量外)を塗ったボウルやタッパーなどの発酵容器に移し、生地が乾燥しないようにラップや固く絞った濡れ布巾をかけます。
温度25℃~28℃程度の暖かい場所で、生地が約2倍の大きさになるまで発酵させましょう。
ホームベーカリーの発酵機能を使うと温度管理が簡単です。
発酵時間は季節や室温で変わりますが、1時間~1時間半が目安となります。
【ポイント】フィンガーチェックで発酵完了を見極める
発酵が終わったかを確認するには「フィンガーチェック」を行います。人差し指に強力粉をつけ、生地の中央にそっと第二関節あたりまで差し込んでみてください。
- 指を抜いた穴がそのまま残る 最適な発酵状態
- 穴がすぐに縮んでしまう 発酵不足
- 指を入れたら生地全体がしぼんだ 過発酵
過発酵になってしまったパン生地は、焼いても美味しくないので、ピザ生地にシフトチェンジするのがおすすめです。
2. ガス抜き・分割・丸め ~生地を整え、分ける~
一次発酵が完了したら、まず「ガス抜き」をします。
生地を手のひらで優しく押さえ、発酵中に発生した大きな炭酸ガスの気泡を潰して、パンのキメを均一に整えます。
その後、スケッパー(カード)などを使って、作りたいパンの数に合わせて生地を切り分け(分割)ます。
それぞれの切り口を内側にしまい込むようにして表面を張らせながら丸めます(丸め)。
3. ベンチタイム ~生地の休憩時間~
分割・丸めで傷み、緊張した状態になったグルテンを休ませるための「休憩時間」がベンチタイムです。
この工程を経ることで、生地が緩んで次の成形作業がしやすくなります。
固く絞った濡れ布巾などをかけ、10分~15分ほど生地を休ませましょう。
4. 成形 ~パンの形を作る~
ベンチタイムが終わったら、作りたいパンの最終的な形に整える「成形」の工程です。
めん棒で生地を伸ばしてガスを抜きながら、具材を包んだり、編んだり、巻いたりします。
ここで生地を触りすぎると傷んでしまうため、手早く行うのがポイントです。
5. 二次発酵(最終発酵) ~焼き上げ前の最終仕上げ
成形した生地を、再び発酵させてふっくらと膨らませます。
温度30℃~35℃、湿度を高めに保った環境で、生地が1.5~2倍の大きさになるまでが目安です。
この工程もホームベーカリーの発酵機能が便利です。
乾燥はパンの膨らみを妨げる大敵なので、霧吹きで軽く水をかけるなどして、乾燥しないように注意してください。
6. 焼成 ~オーブンで焼き上げる~
二次発酵が終わるタイミングを見計らって、オーブンをレシピの指定温度より20℃ほど高く予熱しておきます。
これは、扉の開閉で庫内の温度が下がってしまうためです。
ホームベーカリーの場合は、予熱などはできないので、そのまま内釜の中に入れてスタートボタンを押します。
焼く直前に、つや出しのための溶き卵(ドリール)を塗ったり、模様付けや火通りのための切り込み(クープ)を入れたりします。
準備ができたら、速やかにオーブンに入れ、指定の温度と時間で焼き上げます。
焼き上がったら、パンを型や天板から取り出し、網(クーラー)の上で冷まします。
こうすることで、余分な蒸気が抜けて、外はカリッと、中はふんわりとした食感が保てます。
パンづくりでいちばん大切なのがミキシング
ここまで、パン作りの基本的な流れから、こね上がりの見極め方、そして発酵から焼成までの工程を見てきました。
パン作りには多くの工程がありますが、その中でも全ての土台となるのが「ミキシング(こね)」です。
ミキシング(こね)の状態で、美味しさの80%が決まると言ってもいいです。
いくら良い材料を使っても、発酵や焼成の温度管理を完璧に行っても、最初のミキシングでしっかりとしたグルテン構造を作れていなければ、決して美味しいパンにはなりません。
建物で言えば、ミキシングは「基礎工事」にあたります。
この基礎がしっかりしているからこそ、その後の発酵や焼成といった工程が生きてくるのです。
手ごねには手ごねの楽しさがありますが、毎回安定して完璧な生地をこね上げるのは、慣れていないと難しいものです。
だからこそ、ホームベーカリーの力を借りて、この最も重要で大変なミキシングの工程を任せることには、大きな価値があります。
次のセクションでは、大切なミキシングを助けてくれるホームベーカリーについて、メーカーごとの特徴や、ホームベーカリー以外の選択肢も紹介します。
メーカー別ホームベーカリーのこねる機能と他の選択肢
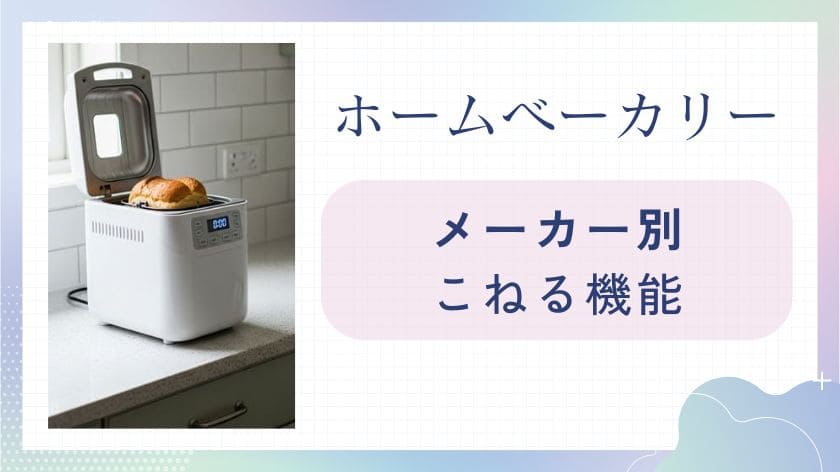
- 定番のパナソニックはマニュアル機能が充実
- シロカで生地作りする時の注意点
- アイリスオーヤマでの生地作り
- 象印での生地作りのやり方
- ツインバードでこねるだけはできる?
- レコルトでの生地作り
- パンこね機との違いとメリット・デメリット
- フードプロセッサーでも可能って本当?
- あなたに合うのはどのタイプ?
- まとめ:ホームベーカリーは「こねるだけでも」大丈夫
定番のパナソニックはマニュアル機能が充実

ホームベーカリーのトップブランドの一つが、パナソニックです。
長年の技術と信頼性で、多くのパン作り愛好家から支持されています。
パナソニックSD-MDX4には、「こねるだけ」と「生地系」のメニューが、8種類あります。
- マニュアル機能「ねり」(1~30分)
- 食パン生地(1時間)
- ハード生地(2時間)
- 立地生地(1時間)
- 天然酵母パン生地(4時間)
- ピザ生地(45分)
- 8分スピード生地(8分)
- うどん・パスタ(15分)
※ マニュアル機能「ねり」と「8分スピード生地」「うどん・パスタ」は、こねるだけで、その他の生地はねりから1次発酵までやってくれます
※ 生地メニューには、ドライイーストが落ちるタイミングと、具材を入れるタイミングを教えてくれるブザーが付いています
(引用:パナソニック公式サイト)
マニュアル機能「ねり」では、時間を設定できるのは当然ですが、羽根の回転速度も設定できます。
パナソニックSD-MDX4で使用できる小麦粉の量は、200~300gです。
生地の状態を確認するときには、かならず一時停止させてから見るようにして下さい。
また、「ねり」にはドライイーストの自動投入機能はないので、あなたが時間を見て入れる必要があります。
さらに、SD-MDX4には、「マイねり」があります。
「マイネリ」機能は、3つまでの連続した「ねり工程(時間・レベル)」を、5パターン設定できるものです。
たとえば、次のような工程を設定できます。
- レベル1 2分
- レベル3 5分
- レベル4 10分
これだけ見ると難しそうですが、パナソニックSD-MDX4のレシピブックには、プロの職人が監修した工程、レシピがしっかり載ってるので安心してください。
「ねり」以外のマニュアル機能
- 発酵 10~120分、レベル1~4
- 焼き 30~50分、レベル1~4
シロカで生地作りする時の注意点
シロカのホームベーカリーは、スタイリッシュなデザインと、比較的手に取りやすい価格帯で人気を集めています。
基本的なパン作り機能はもちろん、ヨーグルトやジャム、お餅なども作れる多機能性が魅力です。
シロカSB-2D151には、「こねるだけ」と「生地系」のメニューが、4種類あります。
- こねる(5~30分)
- パン生地(1時間56分)
- ピザ生地(1時間25分)
- うどん・パスタ生地(20~30分)
※ 「こねる」「うどん・パスタ生地」は、こねるだけで、「パン生地」「ピザ生地」メニューは1次発酵までやってくれます
※ ドライイースト自動投入の機能はないです
※ この4つのメニューには、具材を入れるタイミングを教えてくれるブザーはないです
(引用:シロカ公式サイト)
シロカSB-2D151で使用できる小麦粉の量は、400gまでです。
また、水分の量は、粉の量の半分以上にしてくださいというただし書きがついてます。
生地の状態を確認するときには、かならず一時停止させてから見るようにして下さい。
また、シロカSB-2D151にはドライイーストの自動投入機能は有りません。
はじめからいれるか、あなたが時間を見て入れる必要があります。
「こねる」以外の単独機能
- 発酵 5分~1時間50分
- 焼き 10分~1時間30分
アイリスオーヤマでの生地作り

アイリスオーヤマは、リーズナブルな価格帯でありながら、多彩なメニューを搭載したコストパフォーマンスの高いホームベーカリーを展開しています。
これからパン作りを始めてみたいという方が、最初に手にする一台としても人気です。
アイリスオーヤマIBM-020には、「こねるだけ」と「生地系」のメニューが、4種類あります。
- こねる(5~25分)
- パン生地(2時間)
- ピザ生地(1時間40分)
- うどん・パスタ生地(40分)
※ 「こねる」「うどん・パスタ生地」は、こねるだけで、「パン生地」「ピザ生地」メニューは1次発酵までやってくれます
※ ドライイースト自動投入の機能はないです
※ この4つのメニューには、具材を入れるタイミングを教えてくれるブザーはないです
(引用:アイリスオーヤマ公式サイト)
アイリスオーヤマIBM-020で使用できる小麦粉の量は、410g(2斤分)までです。
生地の状態を確認するときには、かならず一時停止させてから見るようにして下さい。
また、アイリスオーヤマIBM-020にはドライイーストの自動投入機能は有りません。
はじめからいれるか、あなたが時間を見て入れる必要があります。
「こねる」以外の単独機能
- 発酵 5分~1時間50分
- 焼き 10分~1時間30分
象印での生地作りのやり方
炊飯器などで有名な象印も、長年にわたりホームベーカリーを製造している信頼のメーカーです。
「パンくらぶ」というシリーズ名で知られ、しっかりとした作りと安定した焼き上がりに定評があります。
象印BB-ST10には、「こねるだけ」のメニューはなく、「生地系」のメニューが8種類あります。
生地系のコース
- パン生地(ドライイースト+小麦)2時間5分
- パン生地(ドライイースト+国産小麦)2時間5分
- パン生地(ドライイースト+米粉)45分
- パン生地(天然酵母+小麦)4時間5分
- パン生地(天然酵母+国産小麦)4時間5分
- うどん(こね+ねかし+こね)40分
- そば(こね) 15分
- パスタ(こね+ねかし+こね)40分
※ これらのコースにはドライイースト自動投入はないです
※ パン生地のコースには、具材を入れるタイミングを教えてくれるブザーがあります
(引用:象印公式サイト)
象印BB-ST10で使用できる小麦粉の量は、300gまでです。
こねるだけをしたい場合は、「そばコース」を選んでください。15分までですが、こねるだけをしてくれます。
生地の状態を確認するときには、かならず一時停止させてから見るようにして下さい。
また、象印BB-ST10には各工程の時間を調整できるホームメイドコースがあります。
ホームメイドコースの時間設定
- コネ1 0 or 5~15分
- ねかし 0~20分
- コネ2 0 or 5~15分
- 手作業 OFF or 1時間
- 発酵1 0~2時間
- 発酵2 0~2時間
- 発酵3 0~2時間
- 焼き 0~1時間10分
(引用:象印公式サイト)
前回設定の時間が記憶されていますので、ちょっとずつ変更しながら、あなた好みのパンを焼く工程を作れます。
また、発酵、焼きの独立メニューがないのですが、ホームメイドコースを利用すれば大丈夫です。
ホームメイドコースの中の必要ない工程を「0」に設定すれば、ご希望の工程だけを機能させれます。
ツインバードでこねるだけはできる?

ツインバードのホームベーカリーは、何と言ってもその手頃な価格が最大の魅力です。
「ブランパンメーカー」など、健康志向のパン作りに特化したユニークな製品も展開しています。
ツインバードBM-EF38には、「こねるだけ」と「生地系」のメニューが、8種類あります。
- こね(1~15分)
- 低糖質パン生地(1時間10分)
- 低糖質ブランパン生地(1時間2分)
- 食パン生地(2時間11分)
- ソフトパン生地(2時間9分)
- ハードパン生地(2時間16分)
- ピザ生地(1時間26分)
- うどん/パスタ生地(16分)
※ 「こね」「うどん・パスタ生地」は、こねるだけです
※ ドライイースト自動投入の機能はないです
※ 5つのパン生地メニューには、具入れブザーがあります
(引用:ツインバード公式サイト)
ツインバードの「こね」機能は、5分未満の間隔で合計30分以上の連続使用はできません。
たとえば、「15分運転ー3分休止ー15分運転ー3分休止」で動かすと、次の運転はできなくなり、30分以上休ませる必要があります。
なので、ツインバードBM-EF38でこねるときには、「ねかし」の時間を5分以上取ることが大事です。
ツインバードBM-EF38で使用できる小麦粉の量は、250g~350gです。
水分の合計は、かならず粉の分量の半分以上になるようにという但し書きがついています。
生地の状態を確認するときには、かならず一時停止させてから見るようにして下さい。
また、ツインバードBM-EF38にはドライイーストの自動投入機能は有りません。
はじめからいれるか、あなたが時間を見て入れる必要があります。
「こね」以外の単独機能
- 発酵(30℃) 5分~2時間
- 成形発酵(35℃) 5分~2時間
- 焼き 5分~1時間
レコルトでの生地作り
レコルトの「コンパクトベーカリー」は、その名の通り、幅約20cmという非常にコンパクトなサイズです。
さらに、キッチンに置きたくなるようなスタイリッシュなデザインで注目を集めているホームベーカリーです。
レコルトRBK-1には、「こねるだけ」と「生地系」のメニューが、3種類あります。
- こねる(5~30分)
- パン生地(1時間40分)
- ピザ生地(1時間15分)
※ 「パン生地」「ピザ生地」メニューは1次発酵までやってくれます
※ ドライイースト自動投入の機能はないです
※ 「パン生地」には、具入れブザーがあります
(引用:レコルト公式サイト)
レコルトRBK-1で使用できる小麦粉の量は、300gです。
水分の合計が粉の量の半分以上になるようにというただし書きがあります。
生地の状態を確認するときには、かならず一時停止させてから見るようにして下さい。
また、レコルトRBK-1にはドライイーストの自動投入機能は有りません。
はじめからいれるか、あなたが時間を見て入れる必要があります。
「こねる」以外の単独機能
- 発酵 10分~2時間
- 焼き 10分~1時間30分
パンこね機との違いとメリット・デメリット

ミキシングだけを考えるのでしたら、「ホームベーカリー」の他に「パンこね機(ニーダー)」という選択肢もあります。
パンこね機(ニーダー)は、その名の通り、パン生地をこねる(knead)ことに特化した専用の機械です。
では、ホームベーカリーとパンこね機(ニーダー)は、具体的に何が違うのでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| ホームベーカリー | パンこね機 | |
|---|---|---|
| 主な機能 | こね、発酵、焼き上げまで可能 | こねることに特化 |
| こねる力 | 機種によるが、一般的にマイルド | パワフルで力強い |
| 一度に作れる量 | 少なめ(1斤用で粉250g程度) | 大容量(粉600g~1.5kg以上も) |
| 価格 | 比較的安価なモデルからある | 比較的高価 |
| メリット | ・一台で完結できる手軽さ ・コンパクトな機種が多い ・初心者でも扱いやすい | ・理想的なグルテンを形成しやすい ・一度にたくさん作れる ・リッチな生地もしっかりこねられる |
| デメリット | ・パワーが弱めの機種もある ・一度に作れる量が少ない | ・こねる機能しかない ・サイズが大きく場所を取る ・価格が高い |
メリット・デメリットを見比べてみるとおわかりだと思います。
ホームベーカリーが向いてる方は、初心者です。
「まずは手軽にパン作りを始めたい」「焼き上げまで自動でやりたい」といった、とりあえず試してみたい方や、気軽にパンを焼いてみたいという方にホームベーカリーは向いています。
一方で、パンこね機(ニーダー)が向いてるのは、本格的にやりたいという方です。
「一度にたくさんのパンを作りたい」「ホームベーカリーよりランクアップしたい」「より本格的な生地作りを追求したい」という方向けです。
フードプロセッサーでも可能って本当?
実は、ホームベーカリーやパンニーダーがなくても、フードプロセッサーを使ってパン生地をこねることが可能です。
この方法の最大のメリットは、なんと言ってもそのスピードです。
手ごねやホームベーカリーで15分~20分かかるこねの工程が、フードプロセッサーなら、わずか2分前後で完了してしまいます。
ただし、どんなフードプロセッサーでも良いわけではなく、注意点もあります。
フードプロセッサーの刃の種類
フードプロセッサーには、食材を切り刻むための「金属刃」と、パン生地などをこねるための「プラスチック製のパン捏ね羽」が付属している機種があります。
理想は後者のパン捏ね羽を使うことですが、金属刃でも作ることは可能です。
ただし、金属刃は生地を切るように作用するため、グルテンを傷つけやすいとも言われています。
モーターの熱に注意
短時間でパワフルに回転するため、摩擦熱で生地の温度が上がりやすい傾向にあります。
夏場は特に、粉類を冷やしておいたり、非常に冷たい水を使ったりといった工夫が必要です。
こねすぎに注意
時間が短い分、少し回しすぎただけですぐに「こねすぎ」の状態になり、生地がドロドロになってしまうことがあります。
生地のまとまり具合をこまめに確認しながら、慎重に作業を進める必要があります。
すでにご家庭にフードプロセッサーがある方は、一度試してみる価値はあります。
その驚異的な速さは、忙しい日のパン作りにおいて大きな魅力となるでしょう。
あなたに合うのはどのタイプ?

ここまで、「ホームベーカリー」「パンニーダー」「フードプロセッサー」という、生地作りを助けてくれる3つの道具を見てきました。
情報が多くて、結局どれを選べばいいか迷ってしまったかもしれません。
そこで、あなたの目的別に最適なタイプを整理してみましょう。
とにかく手軽に、失敗なくパン作りを始めたい!
ホームベーカリーがおすすめです。
材料を入れてスイッチを押すだけの手軽さは、初心者にとって何よりの魅力。
焼き上げまで全自動でできるので、オーブンがなくてもパンが焼けます。
本格的にパン作りをしたい
パンこね機(ニーダー)が最適です。
大容量の生地を一度に、かつ力強くこね上げることができます。
ホームベーカリーの容量では物足りなくなった方のステップアップにも向いています。
ただし、パンを焼くためのオーブンが必要に鳴りますので、かなりの出費になります。
まだ、パン作りをしたことがなく、本格的にはやりたいけど道具がまったくないかたは、とりあえず安いホームベーカリーで試してみてください。
すでにフードプロセッサー、オーブンを持ってる
まずは、フードプロセッサーを試してみてください。
うまくいけば、そのままフードプロセッサーを使ってパン作りをすればいいです。
ダメなら、ホームベーカリーか、パンこね機を検討してみてください。
また、圧倒的な時間短縮が可能です。
パン生地をなるべく時間かけずにつくりたいのでしたら、フードプロセッサー一択です。
パン作りを趣味にしたい
パンを焼くためのオーブンを持たれていたら、まずは手ごねでパン生地を作って、焼いてみてはどうでしょうか。
何度か試してうまく焼けるようなら、ホームベーカリーかパンこね機を検討すればいいです。
手ごねで焼いた時の経験が、どんな機械を使ってもかならず役に立つはずです。
まずは、いちどパンを焼いてみることをおすすめします。
よくある質問
- ホームベーカリーで「こねるだけ」ってできるの?
-
はい、できます。多くのホームベーカリーには「こねメニュー」や「うどん・パスタコース」など、こねるだけの独立機能が搭載されています。発酵や焼きは自分で管理したい方に便利です。
- パンが膨らまない原因は何?
-
「こね不足」や「こねすぎ」が主な原因です。こね不足だとグルテンが弱くガスを保持できず、こねすぎると生地がダレてしまいます。グルテン膜チェックで生地の状態を確認するのがおすすめです。
- こね時間はどのくらいが目安?
-
一般的には合計20分前後が目安ですが、機種や粉の量、レシピによって変わります。大切なのは時間ではなく「グルテン膜」がしっかりできているかどうかで判断することです。
- どのメーカーのホームベーカリーがおすすめ?
-
パナソニックはマニュアル機能が充実しており、細かく設定可能です。シロカやアイリスオーヤマはリーズナブルでシンプルに使えます。象印は「そばコース」でこね専用に使え、ツインバードやレコルトはコンパクトで価格が手頃です。
- パンこね機(ニーダー)との違いは?
-
ホームベーカリーはこね・発酵・焼きまで1台で可能ですが、こねる力は弱めで容量も少なめです。パンこね機はこね専用でパワフルかつ大容量に対応できますが、オーブンが別に必要で価格も高めです。
- フードプロセッサーでもパン生地をこねられる?
-
はい、可能です。こね専用の羽があれば理想的ですが、金属刃でも短時間で生地をまとめられます。ただし摩擦熱で生地温度が上がりやすいため、冷水や冷やした粉を使う工夫が必要です。
- 初心者にはどの機種や方法が向いてる?
-
まずはホームベーカリーがおすすめです。材料を入れてスイッチを押すだけで焼き上げまで自動ででき、失敗が少ないです。本格的にたくさん作りたい方はパンこね機、すでにフードプロセッサーを持っている方はそちらを試すのもアリです。
まとめ:ホームベーカリーは「こねるだけでも」大丈夫

ここまで、ホームベーカリーの「こねるだけ」機能を中心に、パン作りのコツや様々な道具について見てきました。
パン作りには多くの選択肢がありますが、最初の一歩としては、やはりホームベーカリーが最も心強いパートナーになるでしょう。
ミキシングという最も大変な工程を正確にこなし、時には焼き上げまで全自動で完了してくれる手軽さは、忙しい毎日の中でパン作りを続けるための大きな助けとなります。
まずは一台手に入れて、この記事で紹介したポイントを参考にしながら、気軽に生地作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。
- ホームベーカリーはパンを焼くだけでなく「こねるだけ」でも大丈夫
- パン作りの失敗は「こね不足」「こねすぎ」が原因であることが多い
- こね上がりのベストな状態は「グルテン膜」で確認する
- こねるだけの機能がない機種は「うどん・パスタコース」で代用できる場合がある
- 「パン生地コース」は一次発酵まで自動で便利
- 最適なこね時間は機種やレシピによるが約20分が目安
- 1斤用ホームベーカリーでこねられる粉の量は280g程度
- メーカー指定量を超える使用は故障の原因になるため避けるべき
- パナソニックは細かく設定できる「マニュアル機能」が魅力
- アイリスオーヤマやツインバードは低価格で基本的な機能を備え初心者にも人気
- レコルトはコンパクトでおしゃれ、こね時間の手動設定ができる
- パンこね機(パンニーダー)はこねる機能に特化
- パンこね機(パンニーダー)はパワフルで大容量だが高価
- フードプロセッサーなら約2分でこねられるが温度管理とこねすぎに注意が必要
- 自分の目的やライフスタイルに合わせて最適な道具を選ぶことが大切
ホームベーカリーの使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を守ってください。また、この記事で紹介した方法は、あくまで私個人の経験に基づくものです。アレルギーに関する情報や正確な製品仕様については、必ず各メーカーの公式サイトや専門機関にご確認いただきますよう、お願いいたします。(参考:家電製品PLセンター)