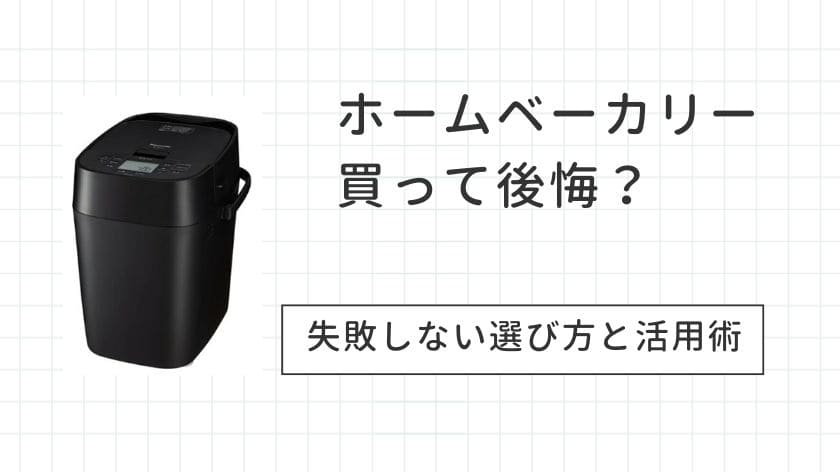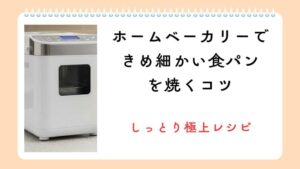「自宅で焼きたてのパンが食べたい」と憧れてホームベーカリーの購入を考えたものの、「買って後悔したらどうしよう…」と、一歩踏み出せないでいませんか。
実際にホームベーカリーを買ってみたものの、買わなきゃよかった、結局やめた、いらなかった、という声があるのも事実です。
その背景には、パン作りに失敗してしまうことや、だんだん使わなくなるという現実があります。
また、食パンを買うのと作るのではどっちが安いのか、気になる電気代や製品の寿命はどれくらいか、といったコストの問題も無視できません。
この記事では、ホームベーカリーを買うべきか悩んでいるあなたのために、判断するための材料をお伝えします。
そして、どんな人におすすめで、逆に買ってはいけないのはどんなタイプか、後悔しないための選び方から、購入後に買って良かったと心から思える使いこなす方法まで、紹介していきます。
実は、わたしもはじめは買って後悔していましたが、今では週5でヘビロテしています・・!
- ホームベーカリーで後悔する人の共通点と失敗する理由
- 買ってはいけない人と心からおすすめできる人の特徴
- 材料費や電気代を含めたコストと製品寿命の実態
- 後悔しないための具体的な選び方と賢い使いこなし術
ホームベーカリー買って後悔する主な理由

- 買ってみた人の後悔する理由とは
- なぜパン作りで失敗する?
- 次第に使わなくなるパターンと原因
- 食パン、買うのと作るのどっちが安い?
- 買わなきゃよかった、やめた人の本音
買ってみた人の後悔する理由とは
ホームベーカリーを購入したものの、後悔してしまう人には4つの共通した理由があります。
憧れだけで購入すると、現実とのギャップに直面することが少なくありません。
まず最も多く聞かれるのが、本体の大きさと置き場所の問題です。
ホームベーカリーは炊飯器と同等か、それ以上に場所を取る家電です。
キッチンの作業スペースが限られている場合、常設する場所を確保できず、使うたびに棚から出し入れすることになります。
この「出す・しまう」という一手間が、徐々に面倒に感じられるようになるのです。
次に、材料を常に揃えておくことのハードルです。
パンを作るには、強力粉、ドライイースト、バター、スキムミルクなど、普段の料理ではあまり使わない材料が必要です。
いざ作ろうと思った時に「イーストを切らしていた」「強力粉が足りない」となると、作る気が一気になくなってしまいます。
これらの材料を常に管理し、ストックしておく手間が、後悔につながる一因です。
さらに、運転時の音を気にする声もあります。
特に夜間に予約タイマーで朝食用に焼く場合、生地をこねる「ウィンウィン」というモーター音や、イーストを自動投入する際の「ガシャン」という音が、睡眠の妨げになると感じる人もいます。
静音設計のモデルも増えていますが、寝室とキッチンの距離が近い場合は注意が必要です。
いちばん大きな問題点は、上記のような手間ひまをかけた割に、スーパーで売ってるパンと、それほど美味しさが変わらないという点です。
やもすれば、スーパーのほうが美味しいと思う方もいらっしゃいます。
そうなってしまうのには理由があるのですが、後悔する理由の最大が、その美味しさの部分です。
- 置き場所の確保
炊飯器並みの大きさで、収納すると出し入れが面倒になる。 - 材料の管理
強力粉やイーストなど、専用の材料を常備する手間がかかる。 - 運転音
特に夜間の予約運転では、こねる音や投入音が気になる場合がある。 - 美味しさ
スーパーで売ってるパンと味がそれほど変わらない
この4つのポイントを良く検討してみることが大切です。
なぜパン作りで失敗する?

「材料を入れてボタンを押すだけ」という手軽さが魅力のホームベーカリーですが、それでもパン作りがうまくいかないケースは少なくありません。
ただ、うまくいかないと言っても焦げてしまったり、とんでもないものができてしまうのではなく、とびきり美味しいというわけではないということです。
そういった「失敗」が続くと作る意欲が失われ、後悔につながります。
失敗の最も大きな理由は、材料の計量が不正確なことです。
パン作りは科学の実験に似ており、粉や水、塩、イーストの量がわずかに違うだけで、膨らみ方や食感が大きく変わってしまいます。
特に、ドライイーストは0.1g単位での調整が求められることもあり、正確なデジタルスケールの使用が不可欠です。
また、材料の選び方も非常に重要です。
特にドライイーストは生き物であり、古くなると発酵する力が弱まり、パンが全く膨らまない原因になります。
強力粉も開封してから時間が経つと風味が落ち、うまく焼き上がらないことがあります。
そもそも、普通の小麦粉ではなく、おいしい小麦粉、たとえば「春よ恋」とか「キタノカオリ」、「銀将」などを使うのが必須です。
季節による室温や水温の変化も、失敗の要因となり得ます。
夏場は水温を低く、冬場は少しぬるま湯にするなど、レシピ通りの分量だけでなく、環境に応じた微調整が必要です。
多くの機種には室温を検知してプログラムを最適化する機能がありますが、基本的な知識がないと、なぜ失敗したのか原因がわからず、挫折しやすくなります。
次第に使わなくなるパターンと原因
購入当初は毎日のようにパンを焼いていたのに、数ヶ月後には戸棚の奥で眠っている…
これはホームベーカリーで「後悔した」と感じる人がたどる、典型的なパターンです。
使わなくなる最大の原因は、「パン作り」という行為が日常のルーティンから外れてしまうことにあります。
最初は焼きたてのパンの美味しさや作る楽しさでモチベーションが高いのですが、その感動も次第に薄れていきます。
すると、材料の計量や後片付けといった「手間」の部分が、焼きたてのパンを食べる「喜び」を上回ってしまうのです。
特に、パンケースや羽根の洗浄は、毎回必ず発生する作業です。
構造が複雑なわけではありませんが、忙しい日々の中では、このわずかな手間さえも負担に感じられることがあります。
また、市販パンの手軽さと多様性も、ホームベーカリー離れを加速させる要因です。
スーパーやパン屋さんに行けば、何もせずとも多種多様な美味しいパンが手に入ります。
今日は超熟、明日はダブルソフト、といったように、気分に合わせて選ぶ楽しみは、ホームベーカリーでは味わえません。
結果として、「たまに焼くのは良いけれど、毎日は大変」と感じ、徐々に使用頻度が落ちていくのです。
食パン、買うのと作るのどっちが安い?

「ホームベーカリーがあれば食費の節約になるのでは?」と考える方は多いですが、実際のところコストパフォーマンスはどうなのでしょうか。
ここでは、市販の食パンと手作りパンのコストを比較してみます。
結論から言うと、材料の選び方や作る頻度によりますが、大幅な節約は難しいのが現実です。
一般的な手作り食パン(1斤)のコストを試算してみましょう。材料費は、使用する粉やバターの価格によって変動します。
| 項目 | 手作りパン(1斤) | 市販の食パン(1斤) |
|---|---|---|
| 材料費・商品価格 | 約150円~200円 | 約100円~500円~ |
| 電気代 | 約20円 | なし |
| 初期費用(本体代) | 月換算で数百円 | なし |
| 合計(目安) | 約170円~ + 初期費用 | 約100円~ |
表からわかるように、スーパーで安く売られている食パンと比較した場合、手作りの方が高くなります。
特に、国産小麦やよつ葉バターなどのこだわりの材料を使えば、材料費はさらに上がります。
しかし、パン屋さんのような高品質なパンと比較すれば、手作りの方が安く作れる可能性があります。
例えば、無添加や特定の材料にこだわった高級食パンは1斤500円以上することもありますが、ホームベーカリーなら同等の品質のものを半額以下で作ることも可能です。
ただ、それには何度も試作したり、パン作りの知識が必要です。
単純な節約目的であれば、ホームベーカリーは最適な選択ではありません。しかし、「安全な材料で作りたい」「焼きたての美味しさを楽しみたい」といった付加価値を重視するならば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。
買わなきゃよかった、やめた人の本音
購入後に「買わなきゃよかった」「使うのをやめた」と感じた人たちの本音には、理想と現実のギャップが色濃く反映されています。
最も多く聞かれるのが、「焼きたては美味しいけれど、時間が経つと市販のパンに劣る」という意見です。
ホームベーカリーで焼いたパンは、保存料などを使用していないため、焼きたての瞬間が美味しさのピークです。
翌日になるとパサついたり、硬くなったりしやすく、いつまでも柔らかい市販のパンの偉大さを再認識する、という声が少なくありません。
また、味のバリエーションに限界を感じるという点も挙げられます。
自分でレーズンやナッツを加えることはできても、お店で売っているような複雑な惣菜パンや菓子パンを作るのは困難です。
毎日同じような素朴な味の食パンが続くと飽きてしまい、結局は様々な種類が並ぶスーパーのパン売り場に戻ってしまうのです。
さらに、パン作りの知識がないまま購入し、期待が大きすぎたためにガッカリした、という声もあります。
うまく膨らまなかったり、食感が悪かったりした時に、原因を突き止めて改善する知識や情熱がないと、「自分には向いていなかった」と諦めてしまいがちです。
ホームベーカリー買って後悔しないための方法

- 買ってはいけない人とどんな人におすすめか
- 買うべきか悩んだ時の選び方のコツ
- 気になる電気代と製品の寿命
- 買って良かったと思える使いこなす方法
- まとめ:ホームベーカリー買って後悔しないために
買ってはいけない人とどんな人におすすめか
ホームベーカリーは、誰にでも合う魔法の家電ではありません。
購入して後悔しないためには、自分のライフスタイルや性格が、ホームベーカリーと相性が良いかを見極めることが重要です。
買ってはいけない人の特徴
以下のような特徴に当てはまる場合、購入しても「宝の持ち腐れ」になってしまう可能性が高いです。
- 手間をかけるのが苦手な人
材料の計量や後片付けが面倒だと感じる人は、いずれ使わなくなるでしょう。 - キッチンのスペースに余裕がない人
本体を常設できる場所がなければ、出し入れが面倒で使わなくなります。 - パンをあまり食べない人
消費量が少ないと、1斤焼いても食べきれず、材料も古くなってしまいます。 - 節約だけが目的の人
前述の通り、市販の安いパンよりコストがかかる場合もあり、節約効果は限定的です。
どんな人におすすめか
一方で、次のような人にとっては、ホームベーカリーは生活の質を格段に上げてくれる最高のパートナーになります。
- パンが大好きで毎日食べる人
焼きたての美味しさを毎日味わえ、長期的に見ればコストメリットも出る可能性があります。 - 添加物が気になる健康志向の人
材料を自分で選べるため、無添加で安全なパンを安心して食べられます。 - パン作りやアレンジを楽しみたい人
生地作りを任せて成形パンに挑戦したり、様々な材料でオリジナルパンを作ったりと、趣味として楽しめます。 - 子育て中の家庭
子どもと一緒にパン作りを楽しんだり、アレルギー対応のパンを作ったりするのに役立ちます。
結局のところ、「パンを食べる」ことよりも「パンを作る」過程や、そこから得られる付加価値に喜びを感じられるかが、満足度を左右する大きな分かれ道と言えそうです。
買うべきか悩んだ時の選び方のコツ

購入を決めた、あるいはまだ迷っているという方のために、後悔しないホームベーカリーの選び方のコツを解説します。
機能や価格だけで選ぶと失敗しやすいため、自分の使い方に合った機種を見つけることが大切です。
1. 容量で選ぶ
一度に焼けるパンの量は、1斤用が主流です。
一人暮らしや二人暮らし、パンの消費が少ない家庭なら1斤で十分です。
家族が多い場合や、一度にたくさん焼いて冷凍したい場合は、1.5斤や2斤対応のモデルも検討しましょう。
ただし、容量が大きくなると本体サイズも大きくなる点には注意が必要です。
2. 自動投入機能の有無
パン作りの成否を分けるドライイーストを、最適なタイミングで自動投入してくれる機能は、初心者にとって非常に心強い味方です。
また、レーズンやナッツなどの具材を自動で投入してくれる機能があれば、具材入りパンも手間なく作れます。
これらの機能は、特に予約タイマーを使う際に真価を発揮します。
3. メニューの豊富さ
食パン以外にも様々なパンを作りたいなら、オートメニューの数を確認しましょう。
全粒粉パン、米粉パン、フランスパン風、生食パンなど、多彩なメニューがあれば飽きずに楽しめます。
さらに、うどん・パスタ生地、ピザ生地、お餅、ジャム、ケーキなど、パン以外のメニューが充実していると、活用の幅がぐっと広がります。
4. 独立モード(マニュアル機能)
パン作りに慣れてきた上級者や、こだわりのパンを作りたい人には、「こね」「発酵」「焼き」の各工程を個別に設定できる独立モードがおすすめです。
生地作りだけをホームベーカリーに任せ、成形してオーブンで焼くなど、より本格的なパン作りに挑戦できます。
主要メーカーの特徴
- パナソニック
「パン作りの王道」と言われるメーカー。イースト自動投入や温度管理技術に定評があり、初心者でも失敗しにくい。特に上位機種「ビストロ」は、本格的なパンが焼けると人気が高いです。 - シロカ
コストパフォーマンスに優れたメーカー。手頃な価格ながら、必要な機能を備えており、初心者でも手を出しやすいのが魅力です。 - アイリスオーヤマ
こちらもコスパに優れ、シンプルな機能とデザインが特徴。基本的な食パンが焼け、見た目もおしゃれなモデルが多いです。
気になる電気代と製品の寿命
ホームベーカリーを導入する上で、見過ごせないのが維持コストと耐久性です。
購入前に、ランニングコストと製品の寿命について把握しておきましょう。
1回あたりの電気代
ホームベーカリーで食パンを1回(1斤)焼くのにかかる電気代は、機種や電力会社との契約によって多少異なりますが、一般的に約20円前後と言われています。
これは、こね、発酵、焼き上げまでの全工程を含んだ金額です。
毎日使ったとしても、月々の電気代は600円程度。思ったよりも経済的だと感じる方が多いのではないでしょうか。
製品の寿命
ホームベーカリーの寿命は、使用頻度やメンテナンス状況によって大きく変わりますが、一般的には5年~10年が目安とされています。
毎日酷使すれば部品の摩耗も早まりますし、逆にたまにしか使わなくても、長期間放置することで故障のリスクが高まることもあります。
寿命を延すためには、日頃のメンテナンスが重要です。
使用後はパンケースや羽根を丁寧に洗浄し、本体の汚れも拭き取るようにしましょう。
特に、パンケースのコーティングが剥がれるとパンがくっつきやすくなり、焼き上がりに影響するため、優しく扱うことが大切です。
長持ちさせるためのポイント
- 使用後は必ずパンケースと羽根を洗浄し、乾燥させる。
- 本体内外の粉や汚れをこまめに拭き取る。
- パンケースを硬いもので擦ったり、衝撃を与えたりしない。
適切な手入れを心がけることで、大切なホームベーカリーと長く付き合っていくことができます。
買って良かったと思える使いこなす方法

ホームベーカリーの真価は、食パンを焼くだけに留まりません。
「買って良かった」と心から満足している人たちは、様々な機能を上手に活用しています。
ここでは、生活を豊かにする使いこなし術を紹介します。
1. 「生地作りコース」を最大限に活用する
最も面倒な「こね」と「一次発酵」までをホームベーカリーに任せられる「パン生地コース」は、活用の幅を広げる最強の機能です。
- ピザ生地
週末のランチに、手作りピザはいかがでしょうか。約45分で生地ができるので、子どもと一緒にトッピングを楽しむのも素敵です。 - 惣菜パン・菓子パン
ウインナーロールやあんぱん、メロンパンなど、成形が必要なパンも気軽に挑戦できます。 - 中華まん生地
冬には、手作りの中華まんもおすすめです。
2. パン以外のメニューに挑戦する
多くのホームベーカリーには、パン以外のメニューも搭載されています。
- お餅
もち米と水を入れるだけで、つきたてのお餅が楽しめます。お正月だけでなく、普段のおやつにもぴったりです。 - 生パスタ・うどん
こねる作業を任せられるので、手打ち麺もぐっと身近になります。 - ジャムやコンポート
季節の果物を使って、無添加の自家製ジャムが手軽に作れます。 - ケーキ
材料を混ぜて焼くだけで、パウンドケーキ風の焼き菓子が完成するモデルもあります。
3. 予約タイマーで豊かな朝を迎える
やはりホームベーカリーの醍醐味は、朝、パンの焼ける香りで目覚めるという体験です。
夜寝る前に材料をセットしておけば、忙しい朝でも焼きたての温かいパンが食卓に並びます。
この豊かな時間の使い方は、一度体験するとやめられなくなる魅力があります。
まとめ:ホームベーカリー買って後悔しないために
最後に、ホームベーカリーを買って後悔しないためのポイントをまとめます。
購入を検討している方は、これらの点を再確認して、自分にとって本当に必要な家電かどうかを判断してください。
- 後悔の主な理由は置き場所、材料管理、運転音、手入れの手間
- 失敗の原因は不正確な計量と古い材料にあることが多い
- 次第に使わなくなるのは手間が楽しさを上回るから
- コストは市販の安価なパンより高くなる可能性がある
- 節約目的より「食の質」を重視する人に向いている
- 焼きたては絶品だが、冷めると硬くなりやすい点を理解する
- 買ってはいけないのは手間が苦手でスペースがない人
- おすすめなのはパン好きで健康志向、アレンジを楽しみたい人
- 選ぶ際は容量、自動投入機能、メニューの豊富さが鍵
- 電気代は1回約20円と経済的、寿命は5年から10年が目安
- 使いこなす秘訣は「生地作りコース」の活用にある
- ピザやお餅などパン以外のメニューも楽しむと飽きない
- 予約タイマーで焼きたての朝食を味わうのが醍醐味
- 購入前に自分のライフスタイルと性格を見極めることが最も重要
- 最終的に「作る楽しみ」を見出せるかが満足度の分かれ道
【安全に関するご注意】
ホームベーカリーは高温になる調理家電です。やけどの危険があるため、特に小さなお子様がいるご家庭では、手の届かない場所に設置するなどの配慮が必要です。また、取扱説明書に記載された禁止事項や注意点を必ず守り、安全にご使用ください。ご不明な点や不具合がある場合は、ご自身で判断せず、必ず製造元のサポートセンターにお問い合わせください。