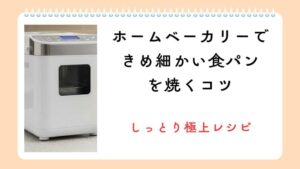焼きたてのパンが自宅で楽しめるホームベーカリー。
「毎日の食パン代を節約できるかも」と購入を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、ホームベーカリーを導入する前に、多くの方が「実際の材料費はいくらかかるの?」「食パンを買うのと作るのどっちが安い?」という疑問を抱きます。
安くパンを作るための節約レシピを探す一方で、パンの原価を計算してみるとコスパが悪いのではないかという声も耳にします。
実は、スーパーで売られてる食パンのほうが安いというのが事実です。
この記事では、その理由と、ホームベーカリーで食パンを一斤いくらで作れるのか、その材料費を徹底的に分析して、できるだけ安くておいしいパンを作る方法をお伝えします。
- 食パン1斤あたりの原価
- 材料費・電気代・本体償却費
- 市販の食パンと手作りパンのコスト比較
- 材料選びや代用品の活用でコストを抑える節約のコツ
- 材料にこだわった場合の費用感と味の変化
ホームベーカリーの材料費、市販パンより高い?

- 食パン、買うのと作るのどっちが安い?
- ホームベーカリーだと一斤いくら?
- かかる費用は材料費だけじゃない~電気代と減価償却費
- 安くパンを作るコスパ最強術
- コスパ以外の魅力は5つ
食パン、買うのと作るのどっちが安い?
わたしの家の近くのスーパーでは、1斤あたり90円で売っています。時には、そこから20%オフになることもあります。
では、ホームベーカリーで作る食パンの1斤あたりのコストは、それに比べるとどうなのでしょうか?
実は、スーパーで安く売られている食パンよりも高くなることがほとんどです。
多くの方が「手作り=安い」というイメージを持っていますが、パン作りに関してはその常識が当てはまらない場合が多いです。
なぜなら、手作りパンには強力粉やドライイースト、バターといった材料費に加え、電気代やホームベーカリー本体の購入費用(減価償却費)も考慮する必要があるからです。
一方で、市販の食パンは製パン工場で大量生産されるため、スケールメリットによって1袋あたりの価格が非常に安く抑えられています。
もちろん、比較対象を高級食パン専門店やこだわりのパン屋さんの食パンにすれば、ホームベーカリーの方が安くなるかもしれません。
しかし、日常的にスーパーで150円前後の食パンを買われていたら、そちらのほうが安くて美味しいパンの可能性が高いです。
節約目的でホームベーカリーを導入するのは、期待通りの結果にならないことが多いです。
ホームベーカリーの購入目的を、コストパフォーマンスはなく、美味しいパンを焼いて食べたいという趣味的な方向に持っていったほうが満足度が高いです。
ホームベーカリーだと一斤いくら?

では、実際にホームベーカリーで食パンを1斤焼くと、材料費はいくらになるのでしょうか。
ここでは、最も基本的な食パンのレシピを例に、具体的な材料費を計算してみます。
材料の価格はスーパーによって変動しますが、わたしの家の近くにあるスーパーの価格で算出しました。
| 材料 | 使用量 | 参考単価 | 1斤あたりの費用 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 250g | 1kg / 398円 | 約100円 |
| バター | 15g | 200g / 450円 | 約34円 |
| 砂糖 | 17g | 1kg / 260円 | 約4円 |
| スキムミルク | 6g | 180g / 380円 | 約13円 |
| 塩 | 5g | 1kg / 110円 | 約0.6円 |
| ドライイースト | 3g | 50g / 300円 | 約18円 |
| 材料費 合計 | 約170円 | ||
このように、ごく一般的な材料を揃えても、材料費だけで1斤あたり約170円かかる計算になります。
これはあくまで目安であり、使用する材料のグレードによって価格は変動します。
かかる費用は材料費だけじゃない~電気代と減価償却費
手作りパンを作る時の費用は、材料費だけじゃないです。
見落としがちなのが、「電気代」と「本体の減価償却費」です。
これらを含めて、1斤あたりのトータルコストを算出してみましょう。
電気代
電気代は次の式で計算できます。
この式をもとに、主要メーカーのホームベーカリーの電気代を計算すると次のようになります。
| メーカー | 機種 | 消費電力 | 時間 | 電気代 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック | SD-MDX4 | 430W | 4時間 | 約53円 |
| シロカ | SB-1D251 | 500W | 3時間53分 | 約62円 |
| 象印 | BB-ST10 | 450W(ヒーター) 69/63W(モーター) | 3時間45分 | 約52円 |
| アイリス | IBM-020 | 550W | 4時間2分 | 約68円 |
電気代は、消費電力をもとに、普通の食パンを1回焼く時を計算したものです。
ただし、はじめから最後まで加熱してたりこねてるわけじゃありません。半分以上の時間を発酵に使ってますので、この電気代は理論上の数値です。
シロカと象印の公式サイトには、電気代についてのアナウンスがあります。
他のメーカーもパンを焼く工程が同じなので、ホームベーカリーで食パンを焼く時の電気代は、1回あたり約10円と考えてもらっていいです。
本体の減価償却費
ホームベーカリーは、使用するたびに少しずつ価値が下がっていきます。
この費用を「減価償却費」といいます。
もっと簡単に言うと、使い始めてから壊れて捨てるまでに焼いた食パンの回数で、購入金額を割ったものです。
ホームベーカリーの寿命を5年として、週2で焼いた場合(520回)を計算してみます。
| メーカー | 機種 | 価格 | 償却費 |
|---|---|---|---|
| パナソニック | SD-MDX4 | 46,956円 | 約90円 |
| シロカ | SB-1D251 | 15,950円 | 約31円 |
| 象印 | BB-ST10 | 32,800円 | 約63円 |
| アイリス | IBM-020 | 10,802円 | 約21円 |
価格は楽天市場の公式サイトの値段です。
減価償却費は車のローンみたいなものです。
はじめに購入費用を一括で払いますが、使うたびにお金を払ってると考えれば、食パンを焼く時の費用と考えられます。
大体、購入費用の0.2%だと思ってもらえればいいです。(1万円なら20円、2万円なら40円)
トータルコスト
これらのコストを合計すると、手作り食パン1斤あたりの真の原価が見えてきます。
| メーカー | 機種 | 材料費 | 電気代 | 償却費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | SD-MDX4 | 約170円 | 約10円 | 約90円 | 約270円 |
| シロカ | SB-1D251 | 約170円 | 約6円 | 約31円 | 約207円 |
| 象印 | BB-ST10 | 約170円 | 約9円 | 約63円 | 約242円 |
| アイリス | IBM-020 | 約170円 | 約10円 | 約21円 | 約201円 |
| 平均 | 約230円 |
普通の食パンをホームベーカリーで焼くと、平均して230円の原価がかかってるのが分かります。
当然ですが、できるだけ安い材料を使って、できるだけ安いホームベーカリーで焼けば、原価は安くなります。
安くパンを作るコスパ最強術

前述の通り、1斤あたりのトータルコストを考えると、手作りパンのコストパフォーマンスは悪いです。
その中でもネックとなるのが、小麦粉などの材料費と償却費です。
そこで、市販されてる90円の食パンに対抗できるようなものをホームベーカリーで焼くにはどうすればいいのか考えてみます。
電気代と減価償却費は、変えることができないので、はじめに計算してしまいます。
まず、電気代を10円にすると、残りが80円になります。
楽天市場で安いホームベーカリーを探してみると、「VERSOS」というメーカーのものが、7,280円で売られていました。
5年で520回使うとして、原価償却費が14円になります。残りが66円となります。
つまり、材料費を66円にすれば、理論上では90円で食パンを焼けることになります。
そこでもう一度、材料費の表を見てください。
| 材料 | 使用量 | 参考単価 | 1斤あたりの費用 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 250g | 1kg / 398円 | 約100円 |
| バター | 15g | 200g / 450円 | 約34円 |
| 砂糖 | 17g | 1kg / 260円 | 約4円 |
| スキムミルク | 6g | 180g / 380円 | 約13円 |
| 塩 | 5g | 1kg / 110円 | 約0.6円 |
| ドライイースト | 3g | 50g / 300円 | 約18円 |
| 材料費 合計 | 約170円 | ||
強力粉が一番高く、170円の半分以上を占めていて、次がバター、ドライイースト、スキムミルクの順番です。
なので、コスパを最強にするには、すべての材料はもちろんですが、特に強力粉とバターとスキムミルクをなるべく安いものにするか、代用品を使う事が必要になります。
特に、強力粉は材料費の中でもウェイトが高いので、なるべく安いものを探す必要があります。
とはいえ、安い粉で作ったものは美味しくないという口コミもあります。
わたしは試したことがないのでなんとも言えないので、味的にもコスパ的にも難しいのではないでしょうか。
ホームベーカリーにはコスパを求めないほうがいいと思われます。
コスパ以外の魅力は5つ
では、ホームベーカリーの魅力は何でしょうか?
ホームベーカリーの魅力は人それぞれですが、わたしは5つほどあると思っています。
- 材料を自分で選べる
- 焼きたてパンが食べられる
- 材料をいれるだけ
- バリエーションが豊富
- 子どもや家族と楽しめる
材料を自分で選べる
最大のメリットが、自分で選んだ材料でパンが作れることです。
たとえば、次のような感じです。
- 好みの小麦粉(国産や有機栽培など)を使う
- グルテンフリーにもできる
- バターの代わりにオリーブオイルを使う
- 砂糖の代わりにハチミツを使う
- 乳製品を代用品に置き換えられる
焼きたてパンが食べられる
ホームベーカリーの魅力は、焼きたてのパンを自宅で味わえることです。
タイマーをセットしておけば、朝起きた瞬間にふわっと香ばしいパンの香りが広がります。
外はパリッと、中はもっちり。出来たての美味しさは、市販のパンでは味わえない特別なものです。
材料をいれるだけ
ホームベーカリーの使い方はとても簡単です。
計量した材料をパンケースに入れて、メニューを選んでスタートボタンを押すだけ。
こね・発酵・焼き上げまで全て自動で行ってくれるので、手間がかかりません。
気軽に手作りパンが楽しめます。
バリエーションが豊富
ホームベーカリーには食パンだけでなく、いろいろなメニューがあります。
フランスパン風や全粒粉パン、米粉パンはもちろん、ピザ生地、うどん、そば、パスタ、おもち、ジャムなど、機種によって違いがありますが、多彩なメニューです。
材料や設定を変えるだけで、毎日の食卓に変化が生まれ、飽きずに楽しめます。
子どもや家族と楽しめる
ホームベーカリーは、家族みんなで楽しめるキッチン家電です。
材料を一緒に量ったり、好きな具材を選んだりする工程は、子どもにとってもワクワクする体験。
食育にもつながり、子どもや家族と一緒に作ったパンは格別の味になります。
休日の朝や特別な日の思い出作りにもぴったりです。
これら「安心感」や「美味しさ」に加えて、パン作りという趣味的を気軽に楽しめることがホームベーカリーの価値と言えます。
ホームベーカリーの材料費~目的別コスト解説
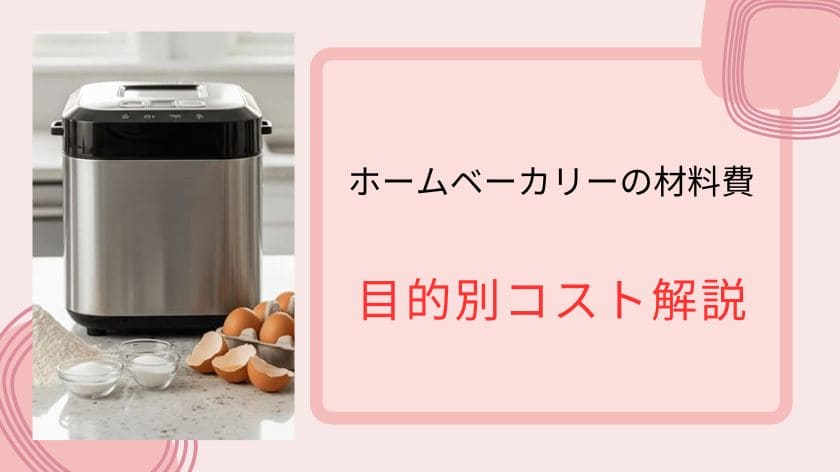
- 食パンを作るのに必要な材料は?
- 強力粉の役割と価格
- 水の役割と種類
- ドライイーストの役割と価格
- 塩の役割と価格、代用品はあるの?
- 砂糖の役割と価格、代用品は?
- バター(油脂)の役割と価格と代用品
- スキムミルクの役割と価格、代りは?
- アレンジで加える材料
- 材料費を安く抑えるには?
- 材料費を抑える節約レシピのコツ
- まとめ:ホームベーカリーの材料費について
食パンを作るのに必要な材料は?
食パン作りの土台となるのは、以下の7つの材料です。
これらが揃っていれば、シンプルな食パンを焼くことができます。
- 強力粉
- 水
- ドライイースト
- 塩
- 砂糖
- バター(油脂)
- スキムミルク
もっと極端に言えば、強力粉、水、ドライイースト、塩の4つがあれば、なんとかパンを焼くことができます。
強力粉の役割と価格

ホームベーカリーでパンを作る上で、最も重要で、かつ材料費の大部分を占めるのが「強力粉」です。
この強力粉の選び方一つで、パンの食感や風味が大きく変わり、同時に1斤あたりのコストも大きく変動します。
強力粉がパン作りに欠かせない理由
強力粉は、お菓子作りに使われる薄力粉や、うどんに使われる中力粉に比べて、タンパク質の含有量が非常に多いのが特徴です。
このタンパク質に水を加えてこねることで、「グルテン」という粘りと弾力性のある網目状の組織が作られます。
このグルテンが、イーストが生み出す炭酸ガスを風船のように内部に閉じ込めてくれます。
その結果、パンはふっくらと膨らみ、オーブンで焼いた後もその形を保つことができるのです。
また、パン独特の「もっちり」「しっとり」とした食感も、この強力なグルテンの網目構造によって生み出されます。
強力粉の価格帯と選び方
強力粉の価格は、「産地・銘柄」によって大きく異なります。
スーパーで手軽に購入できる1kgあたり200~500円前後の安価な強力粉の多くは、輸入小麦を原料としています。
一方で、製菓材料店やネット通販で人気の国産小麦は、豊かな風味ともっちりした食感が特徴です。
価格は1kgあたり400〜800円ほどになります。
特に、「春よ恋」や「はるゆたか」といった北海道産の銘柄は、パン好きの間で非常に人気が高く、これらを使うだけでパンの味が格段にグレードアップします。
| 種類 | 1kgあたり | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般的な強力粉(外国産) | 約200円~400円 | 価格が安く、安定して手に入る。釜伸びが良く、ふっくらと焼き上がる |
| 国産強力粉(春よ恋など) | 約400円~800円 | 風味が豊かで、噛むほどに甘みを感じる。しっとり・もっちりした食感が特徴 |
| 業務用・大容量品 | (1kgあたり200円台も) | ネット通販や業務用スーパーで5kg以上の大袋を購入すると、1kgあた年の単価が安くなる |
初めてパン作りをされる方や、まずはコストを抑えたいという方は、スーパーで手に入る一般的な強力粉で十分です。
しかし、パン作りに慣れてきて、「もっと美味しいパンを焼いてみたい!」と感じたら、ぜひ一度、国産小麦を試してみてください。
水の役割と種類
パン作りの材料として大事なものの一つが「水」です。
「水」は生地の出来を左右する非常に重要な役割を担っています。
パン作りにおける水の重要な役割
水は、美味しいパンを焼き上げるために、3つの重要な働きをしています。
- 生地の形成
強力粉をはじめとする粉類の材料に水分を与え、一つのまとまった生地(パン生地)を作り上げます。 - グルテンの活性化
強力粉に含まれるタンパク質と結合し、パンの骨格となる「グルテン」の網目構造を作り出すきっかけとなります。 - イーストの活性化
乾燥しているドライイーストに水分を与えて「目覚め」させ、パンを膨らませるための発酵活動を開始させます。
季節に合わせた水温調整
忘れてはならないのが「水温」のコントロールです。
イーストは生き物であり、温度によって活動の活発さが大きく変わります。
パン生地が発酵するのに最適な温度は、一般的に27℃前後とされています。
そのため、室温に合わせて水の温度を調整することが、パン作り成功の鍵となります。
- 夏場など室温が高い時期
生地の温度が上がりすぎ、発酵が進みすぎる「過発酵」を防ぐため、冷水を使う。室温が25℃以上の場合は、水温を5℃位に冷蔵庫で冷やしたものを使う - 冬場など室温が低い時期
イーストの活動を促し、適切な発酵状態に導くため、ぬるま湯を使う。室温が10℃以下なら、水温を20度位に温めたものを使う
多くのホームベーカリーには冷却機能がないため、特に夏場の水温管理は失敗を防ぐための重要なポイントです。
水の価格はほぼゼロ
材料費を考える上で、水の価格は「ほぼ0円」と考えて問題ありません。
日本の水道水は非常に安価であり、食パン1斤で使う180ml程度の水の費用は、計算上でも1円をはるかに下回ります。
そのため、パンの原価計算に含める必要はほとんどないでしょう。
ちなみに、パン作りに凝り始めると、「ミネラルウォーターを使った方が美味しくなる?」と考える方もいるかもしれません。
確かに、水の硬度(軟水・硬水)がグルテンの働きに影響を与えますが、基本的にはご家庭の水道水で全く問題ありません。
ただし、フランスパン風のものを作る場合には、コントレックスなどを入れて硬度を上げたほうが良いという人もいらっしゃいます。
ドライイーストの役割と価格

パンを作るために絶対に欠かせない材料、それが「ドライイースト」です。
日本語では「酵母」とも呼ばれるこの小さな微生物が、パン作りの心臓部とも言える重要な役割を担っています。
パンを膨らませる「発酵」の主役
ドライイーストは、普段は眠っている状態の酵母菌です。
これが水と砂糖(栄養)と適切な温度を与えられることで目を覚まし、活発な活動「発酵」を始めます。
発酵の過程で、イーストは生地の中の糖分を分解し、「炭酸ガス」と微量のアルコールを生成します。
この炭酸ガスが、強力粉によって作られたグルテンの網目構造の中に閉じ込められることで、生地が風船のように膨らみます。
これが、パンがふっくらと焼き上がる仕組みです。
発酵時に生まれるアルコールなどの副産物は、パン特有の豊かな風味(フレーバー)を生み出す元にもなります。
つまり、ドライイーストはパンを膨らませるだけでなく、美味しさにも深く関わっているのです。
使用する量は1斤あたりわずか3g程度と少量ですが、その働きは絶大で、パン作りにはなくてはならない存在です。
ドライイーストの種類と価格
ドライイーストは、少量しか使わないからこそ、その種類にこだわるとパンの風味が大きく変わります。
価格も種類によって様々です。
スーパーでよく見かけるのは、3gずつ個包装になったタイプで、使い切りで便利な反面、1gあたりの価格は割高になります。
パンを頻繁に焼くのであれば、製菓材料店やネット通販で100g以上の缶や袋入りのものを購入すると、コストを大幅に抑えることができます。
また、一般的なドライイーストの他に、果物や穀物などに付着している酵母菌を分離・培養した「天然酵母」も人気があります。
例えば、世界遺産・白神山地のブナの原生林から採取された「白神こだま酵母」や、北海道十勝地方のエゾヤマザクラのサクランボから生まれた「とかち野酵母」などが有名です。
これら天然酵母は、それぞれ独特の風味と香りがあり、パンの味に深みを与えてくれますが、その分価格は高価になります。
| 種類 | 1回(3g)あたり | 特徴 |
|---|---|---|
| ドライイースト (サフ赤や日新など) | 約20円~ | 発酵力が安定しており、価格も手頃。どんなパンにも合うオールマイティなタイプ。 |
| 天然酵母 (白神こだま酵母など) | 約50円~ | 酵母由来の豊かな風味と香りを楽しめる。発酵力は穏やかで、しっとりしたパンに仕上がる。 |
はじめは、コストパフォーマンスに優れた一般的なドライイーストで十分です。
慣れてきたり、味の違いを楽しみたい時に、少し高価な天然酵母を使ってみる、といった使い分けをするのがおすすめです。
酵母を変えるだけで、いつもの食パンが全く違う表情を見せてくれます。
塩の役割と価格、代用品はあるの?
パン作りの材料の中で、最も少量ながら、パンの味と品質に絶大な影響を与えるのが「塩」です。
たった数グラムの違いが、パンの出来栄えを大きく左右します。
その重要な役割と、価格、そして代用品の有無について見ていきます。
味だけじゃない!塩の3つの重要な役割
「塩は味付けのために入れる」と思われがちですが、パン作りにおける役割はそれだけではありません。
主に3つの重要な働きをしています。
- 味の引き締めと風味の向上
- 発酵のコントロール
- グルテンの強化
味の引き締めと風味の向上が、最も分かりやすい役割です。
塩は、小麦粉本来の甘みやバターの風味を引き出し、パン全体の味を引き締めます。
塩がなければ、どこか物足りない、ぼやけた味のパンになってしまいます。
最も大事なのが発酵のコントロールです。
塩には、イーストの活動を穏やかにする働きがあります。
塩が生地中の水分を抱え込むことで、イーストの過剰な活動を抑制し、発酵が暴走するのを防ぎます。
これにより、生地は安定してゆっくりと膨らみ、きめ細かい内層のパンが焼き上がります。
3つ目は、グルテンの強化です。
塩は、パンの骨格であるグルテンの網目構造を強く引き締める効果があります。
グルテンが強化されると、生地のベたつきが抑えられて扱いやすくなるだけでなく、ガスを保持する力も強まり、ふっくらとボリュームのあるパンに仕上がります。
このように、塩は「味」「発酵」「骨格」という、パン作りの根幹をなす3つの要素すべてに関わる、まさに縁の下の力持ちなのです。
塩の価格
パンの原価を計算する上で、塩の価格は水と同様に、ほとんど気にする必要はありません。
一般的な食塩は1kgあたり100円前後と非常に安価で、食パン1斤に使う5g程度のコストは1円にも満たないためです。
もちろん、ミネラル豊富な岩塩や天日塩など、こだわりの塩もたくさんあります。
これらは一般的な食塩よりも高価ですが、パン全体のコストに与える影響はごくわずかです。
風味の違いを楽しむために試してみるのも良いですが、基本的にはご家庭にある普通の食塩で全く問題ありません。
塩に代用品はある?
パン作りにおいて、塩の代わりになるものは基本的にありません。
前述の通り、塩が持つ「味の引き締め」「発酵の抑制」「グルテンの強化」という3つの役割を、他の食材で同時に代替することは極めて困難だからです。
もし塩を入れ忘れてしまうと、パン作りは失敗する可能性が非常に高くなります。
生地はベタベタで扱いにくく、発酵が進みすぎてイーストの力がなくなり、焼いても膨らまないか、一度膨らんでもしぼんでしまいます。
味も風味も感じられない、美味しくないパンになってしまうでしょう。
健康上の理由で減塩を心掛けている方もいらっしゃるかもしれませんが、パン作りに関してはレシピ通りの塩を使うことを強くお勧めします。
小麦粉やバター、酵母は好みに合わせて変える楽しみがありますが、塩だけはレシピの指示量を守ることが、美味しいパンを焼くための大切なルールです。
砂糖の役割と価格、代用品は?

パンに優しい甘みと美しい焼き色を与えてくれる「砂糖」。
この砂糖もまた、単なる甘味料としてだけでなく、パンを美味しく焼き上げるために欠かせない、いくつもの重要な役割を持っています。
イーストの栄養源としての重要な役割
パン作りにおける砂糖の最も大切な役割は、「イーストの栄養源(エサ)になる」ことです。
イーストは、砂糖の糖分をエネルギー源として分解し、発酵活動を行います。
砂糖が十分にあることで、イーストは活発に炭酸ガスを生成し、パンを力強く膨らませることができるのです。
その他にも、砂糖には以下のような役割があります。
- 風味と甘み
パン生地に優しい甘みを加え、塩味とのバランスを取ることで、味に深みを与えます。 - 美しい焼き色
生地表面の糖分が、焼成時の熱によってカラメル化することで、食欲をそそる美味しそうなきつね色の焼き色がつきます。 - 保湿効果
砂糖には水分を保つ性質(保水性)があるため、パンのしっとり感を長持ちさせ、硬くなるのを遅らせる効果も期待できます。
砂糖の価格
原価計算において、砂糖の価格も塩や水と同様に、ほとんど気にする必要はありません。
スーパーで一般的に手に入る上白糖やグラニュー糖は1kgあたり200円~と安価であり、食パン1斤に使う17g程度のコストは5円前後です。
パン作りにおいては、きび砂糖やてんさい糖など、こだわりの砂糖を使うこともできますが、味への影響はバターや強力粉ほど劇的なものではありません。
コストを重視する場合は、ご家庭にある一般的な砂糖で全く問題なく、美味しいパンが焼けます。
砂糖の代用品
塩とは異なり、砂糖には風味豊かな代用品がたくさんあります。
代用品を使うことで、いつもの食パンとは一味違った、個性的なパン作りを楽しむことができます。
| 代用品 | 風味・食感への影響 | 使用上のポイント |
|---|---|---|
| はちみつ | 特有の豊かな香りとコクが加わる。パンがしっとりと仕上がる。 | 液体なので、レシピの水分量を少し減らすと良い。焼き色がつきやすい。 |
| メープルシロップ | 上品で香ばしい風味が特徴。優しい甘みのパンになる。 | はちみつ同様、水分量の調整が必要。 |
| 黒糖(黒砂糖) | ミネラル豊富で、深くコクのある独特の風味がつく。パンの色も濃くなる。 | 固形の場合は細かく砕くか、少量のお湯で溶かしてから使うと混ざりやすい。 |
| 三温糖 | 上白糖よりもしっかりとしたコクと優しい甘みが特徴。 | 上白糖とほぼ同じように使えるため、手軽に風味を変えたい時におすすめ。 |
砂糖を他の甘味料に変えるのは、パン作りを手軽に楽しむための第一歩として非常におすすめです。
例えば、いつもの砂糖を黒糖に変えるだけで、驚くほど風味豊かな黒糖パンが焼き上がります。
バター(油脂)の役割と価格と代用品
パンに豊かな風味とコク、そしてしっとりとした食感を与えてくれるのが「バター」に代表される油脂です。
強力粉の次にパンの味を決定づける重要な材料であり、コスト面でも大きな割合を占めます。
ここでは、油脂がパンに与える影響、バターの価格、そしてコストを抑えるための代用品について解説します。
パン作りにおける油脂の役割
油脂は、パンの「美味しさ」と「品質」を向上させるために、いくつもの重要な役割を果たしています。
- 風味とコクの向上
特にバターを使った場合、その乳製品特有の豊かな香りと深いコクがパンの味わいを格段にリッチにします。 - しっとり感と柔らかさの維持
油脂がグルテンの組織をコーティングすることで、生地の伸びが良くなり、きめ細かく柔らかな食感に仕上がります。 - 老化の防止
パンに含まれる水分が蒸発するのを防ぐ効果があり、焼き上がったパンが硬くなる(老化する)のを遅らせてくれます。
ちなみに、フランスパンには、油脂を全く使われません。
そのため、油脂は必須材料ではないとも言えますが、私たちが普段食べているような柔らかい食パンを作る上では、美味しさと食感を左右する非常に重要な役割を担っているのです。
バターの価格
バターは、食パン1斤あたり10g程度しか使いませんが、単価が高いため材料費全体に与える影響は小さくありません。
スーパーで一般的に売られている200gで450円前後のバターを使うと、1回のパン作りで約23円位のコストがかかります。
さらに、味にこだわって高級なバターを選ぶと、コストはさらに上がります。
- よつ葉バター
北海道産の良質な生乳から作られ、ミルクの風味が強いのが特徴。 - カルピスバター
上品でスッキリとした味わいが特徴の高級バター。 - 発酵バター
乳酸菌で発酵させて作るため、ヨーグルトのような独特の芳醇な香りが楽しめます。
これらのバターは、パンの風味を格段に引き上げてくれますが、その分価格も高くなります。
美味しさを追求すればするほど、材料費は上がっていきます。
バターの代用品でコストカット
「バターの風味は魅力的だけど、もう少しコストを抑えたい…」という場合には、他の油脂で代用することも可能です。
代用品によって風味や食感が変わるため、好みに合わせて使い分けるのも良いでしょう。
| 代用品 | コスト比較 | 風味・食感への影響 |
|---|---|---|
| マーガリン | バターより安価 | バターに比べて風味はあっさり。製品によってはパンがふんわりと仕上がる。 |
| ショートニング | バターより安価 | 無味無臭で、焼き上がりがサクッと軽くなる。お菓子作りにも使われる。 |
| サラダ油 | 非常に安価 | 風味にクセがなく、しっとりと仕上がる。最もコストを抑えられる選択肢の一つ。 |
| オリーブオイル | バターと同等 | 特有のフルーティーな香りがつく。ハーブなどを加えた食事パンとの相性が良い。 |
わたし的には、バターを使った時の豊かな風味が一番のおすすめです。
しかし、毎日の食卓に並べるパンであれば、コストを考えてマーガリンやサラダ油を使うのも賢い選択です。
また、作るパンの種類によって油脂を使い分けるのも楽しいです。
例えば、ピザ生地を作る際にはオリーブオイルを使うと、本格的な味わいに近づきます。
スキムミルクの役割と価格、代りは?

ホームベーカリーのレシピでよく見かける「スキムミルク」。
これは牛乳から脂肪分を取り除いて粉末状にした、いわゆる「脱脂粉乳」のことです。
必須の材料ではありませんが、加えることでパンの品質を手軽にワンランクアップさせてくれる、名脇役とも言える存在です。
パンの風味と食感をリッチにする役割
スキムミルクを生地に加えることには、主に4つのメリットがあります。
- 風味とコクの向上
ほのかなミルクの風味が加わり、パンの味わいに深みとコクが生まれます。水だけで作るパンに比べて、よりリッチな味わいになります。 - きめ細かい食感
牛乳に含まれるタンパク質が、グルテンの働きを助け、パン生地のきめを細かく、ふんわりとソフトな食感に仕上げてくれます。 - 美しい焼き色
スキムミルクに含まれる乳糖が、焼成時に美しい焼き色を生み出す手助けをします。イーストは乳頭を分解できないからです。香ばしく、美味しそうな見た目に仕上がります。 - 栄養価のアップ
牛乳由来のカルシウムなどの栄養を手軽にプラスすることができます。
スキムミルクは、いわばパンの「品質向上剤」のような役割を果たします。
必ず入れなければいけないものではありませんが、加えるだけでパン全体の完成度を高めてくれる便利な材料です。
スキムミルクの価格
スキムミルクの価格は、1袋(約180g)で500円前後が相場です。
食パン1斤に使う量は6g程度とごく少量なので、1回あたりのコストは約17円位となります。
バターほど高価ではありませんが、積み重なると全体の材料費に影響を与えます。
粉末状で保存期間が長いため、一度購入すれば長く使えるのがメリットです。
スキムミルクにもブランドがあり、よつ葉乳業や森永乳業、雪印などが有名です。
大手スーパーの製菓材料コーナーなどで手に入れられます。
スキムミルクの代用品は?
「スキムミルクを買い忘れた」「コストを抑えたい」という場合、他のもので代用したり、省略したりすることも可能です。
最も一般的な代用方法が、牛乳を使うことです。
スキムミルクよりもさらに豊かな風味とコクが加わり、よりリッチなパンに仕上がります。
牛乳は液体なので、レシピに記載されている「水」の分量の一部を牛乳に置き換える形で使います。
牛乳の固形分は10%なので、レシピに書かれてるスキムミルクの量の10倍の牛乳を入れます。
そのかわりに、牛乳の水分を加える水から引きます。
例えば、レシピの水分が「水180ml」でスキムミルクが6gの場合、「牛乳60ml+水120ml」のように水分量を調整すします。
この調整を忘れると、生地が水分過多でベタベタになってしまいます。
また、スキムミルクは、レシピから完全に省略してもパンは作れます。
実際に、節約のためにスキムミルクを使わずにパンを焼いている方も多くいます。
省略した場合、ミルクの風味やコクはなくなりますが、小麦本来の味をストレートに楽しめる、あっさりとした素朴な味わいのパンになります。
まずは一度、省略して作ってみて、物足りなさを感じるようであれば、次に牛乳やスキムミルクを加えて味の違いを比べてみ手もいいかもしれません。
色々試してみるのも、パン作りのおもしろさです。
アレンジで加える材料
基本の材料に慣れてきたら、様々な材料を加えてアレンジパンに挑戦するのもおすすめです。
- ナッツ類(くるみ、アーモンドなど)
- ドライフルーツ(レーズン、クランベリーなど)
- チーズ
- ココアパウダーや抹茶パウダー
- ベーコンやコーン
他にも色々ありますし、加え方はそれぞれの機種によって違ってきます。
「ホームベーカリー ナッツ」などで検索して、レシピを調べてみてください。
材料費を安く抑える購入方法は?

「できるだけ安くパンを作りたい!」という方のために、材料費を抑えるための選び方をご紹介します。
材料費を抑えるには、購入先を工夫します。
- 業務用スーパーの活用
大容量の強力粉やバター、ドライイーストが市価よりも安く販売されています。特に1kg以上の強力粉は割安感があります。 - ネット通販でのまとめ買い
頻繁にパンを焼くなら、ネット通販で強力粉を5kgや10kg単位でまとめ買いすると、1kgあたりの単価を大幅に下げられます。また、ブラックフライデーなどのセールやポイントを利用するとお得に購入できます。 - プライベートブランド(PB)商品の選択
スーパー各社が展開するプライベートブランドの材料は、ナショナルブランド品に比べて価格が抑えられている傾向にあります。
材料費を抑える節約レシピのコツ
材料選びだけでなく、レシピを少し工夫することでも材料費の節約に繋がります。
上述したように、高価な材料を別の安価な材料で代用したり、一部の材料を省略したりする方法です。
節約レシピは実験のようなもので、たった一つの正解はありません。
はじめから成功しようとは思わず、「これをなくしたらどうなるのか?」「これで代用できるのか?」など、テーマを決めて試していくことをおすすめします。
それが、面白さや楽しみの一つにつながっていきます。
また、ある人にとっては「バターの風味は絶対に譲れない」、またある人にとっては「スキムミルクはなくても全く気にならない」というように、価値観は人それぞれです。
大切なのは、ネットで探した節約のコツを参考にしながら、あなた自身で試行錯誤を繰り返してみることです。
- 「今日はバターをサラダ油にしてみよう」
- 「次はスキムミルクなしで焼いてみよう」
このように、一度に一つの要素だけを変えて、味や食感、そしてコストがどう変化したかを記録していくと、あなたの好みに合った「わたしだけの黄金レシピ」が必ず見つかります。
少し失敗したとしても、それもまた手作りならではの経験です。
お子さんやご家族と一緒に、パン作りのプロセスを楽しむのがホームベーカリーと言えるかもしれません。
まとめ:ホームベーカリーの材料費について

この記事では、ホームベーカリーの材料費について解説してきました。
最後に、全体の要点をリスト形式でまとめます。
- ホームベーカリーのパンは、スーパーの安価な食パンより高コストである
- 手作りパンの原価は材料費、電気代、本体の減価償却費で構成される
- 基本的な食パン1斤の材料費は約170円が目安である
- 1回あたりの電気代は約10円程度かかる
- 本体の減価償却費は機種価格に依存し、1回あたり数十円のコストとなる
- 材料費の中で最も大きな割合を占めるのは強力粉である
- バターやドライイーストも材料費を押し上げる要因となる
- コスト削減には安価な材料への変更や代用品の活用が有効である
- スキムミルクの省略やバターの油脂への変更はコストカットに繋がる
- 最大限の節約をしても、市販の最安値パンの価格実現は困難である
- 国産小麦など高級食材の使用は、味を向上させるがコストも大幅に上げる
- ホームベーカリーの価値は、節約よりも趣味的な側面に存在する
- 添加物を使わず、自分で選んだ安全な材料でパンが作れる
- 焼きたての味や香りは、市販品では得られない大きな魅力である
- パン作りの工程そのものを家族と楽しむことができる
- ホームベーカリーはパン作りを趣味にするための道具
【安全に関するご注意】
ホームベーカリーは高温になる調理家電です。やけどの危険があるため、特に小さなお子様がいるご家庭では、手の届かない場所に設置するなどの配慮が必要です。また、取扱説明書に記載された禁止事項や注意点を必ず守り、安全にご使用ください。ご不明な点や不具合がある場合は、ご自身で判断せず、必ず製造元のサポートセンターにお問い合わせください。