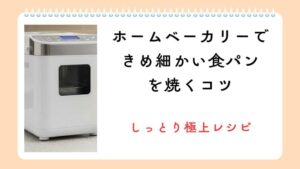ホームベーカリーがあれば、お正月以外でも、つきたての美味しいお餅が、簡単にあなたの家で楽しめます。
ただ、「ホームベーカリーの餅は美味しくない」という声を聞くと、購入をためらってしまうのも仕方ありません。
実際に口コミを見てみると、お餅が硬い、あるいは逆に柔らかすぎるといった失敗だったり、餅粒が残るざらついた食感にがっかりしたという声があります。
わたし自身も、うまくいくときもあれば、何故かダメだったときがありました。
そこで、いろいろ試した経験から、ホームベーカリーで美味しいお餅を作る際のコツや注意点などを簡単に、わかりやすくお伝えします。
そもそも、固くならない餅のつき方や、もち米を水に浸すべきなのか、餅つき機能ありなしで何が違うのか、パナソニックやシロカなどはどれを選べば良いのか、わからないと思います。
さらに、炊飯器や蒸し器でもち米を下処理して、ホームベーカリーでつくだけの方法や、餅つき機との違いも紹介します。
最後まで読んでもらえれば、好きな時に美味しい餅を作れて、あなたにピッタリのホームベーカリーを選べるようになります。
- ホームベーカリーの餅が美味しくないと言われる理由
- 失敗しないための具体的な水分量やもち米の扱い方
- 人気メーカー(パナソニック・シロカ)の餅つき機能の特徴
- つきたて餅を長く楽しむための保存方法やお手入れのコツ
ホームベーカリーの餅が美味しくないと感じる理由

- ホームベーカリーでの餅の美味しくない失敗談
- もち米と水の量が間違えるという本当の意味
- べちゃべちゃで柔らかすぎになる原因
- つきたてなのに硬いのはなぜ?
- ぶつぶつとした餅粒が残る悩み
- もち米を水に浸すのは本当に不要?
- 失敗しない餅のつき方は水分量が鍵
- コツを押さえれば美味しいお餅に!
ホームベーカリーでの餅の美味しくない失敗談

「ホームベーカリーでお餅を作ってみたけれど、なんだか美味しくない…」
という経験は、実は珍しいことではありません。
わたし自身も、初めて挑戦したときは理想通りにいかず、がっかりした記憶があります。
多くの方が経験する失敗は、主に3つのパターンに分けられます。
- ベチャベチャ、ドロドロ
- カチカチに硬く、ボソボソとした食感
- お餅の中に米粒の芯が残る
これらの失敗は、もち米と水の量を間違えたという単純な理由ではないです。
というのも、普通の人だったら、レシピ通りに重さや量を守ってホームベーカリーに入れるはずだからです。
レシピ通りにやっても、失敗するというのが、多くの方の悩みなんです。
もち米と水の量が間違えるという本当の意味
通常、もち米をお餅にするときには、一晩くらい浸水させて、蒸してから杵(きね)でついてお餅にします。
なので、目一杯浸水させてから蒸すので、美味しいお餅になるんです。
ですが、ホームベーカリーの場合は、もち米を水で洗って、30分くらい水切りをしてから、すぐにホームベーカリーに入れて加熱してコネます。
その段階で、人によって水分量が変わってきてしまうんです。
もち米の特徴として、通常のごはんであるうるち米よりも吸水率が高く、素早く水を吸収します。
ですが、古米と新米では吸水率が違いますし、銘柄や気温、水温などによっても違います。
また、人によって、30分くらいが40分になったり、なにか用事をしていて1時間になるときもあるはずです。
そういったもち米の中に給水された水と、ホームベーカリーの内釜に入れる水の量がアンバランスになってしまい、上記のような残念な結果になってしまうと考えられます。
それぞれの失敗の原因をもう少し詳しく見ていきます。
べちゃべちゃで柔らかすぎになる原因

ベチャベチャで、まとまらないほど柔らかく、ドロッとした仕上がりになってしまうと美味しくないですよね。
これは、水分量が多すぎることが根本的な理由です。
取扱説明書通りの水分量でも柔らかすぎるときに考えられるのは、主に2つのポイントです。
- 水切りが不十分だった
- 水に浸しすぎた
もち米を洗った後、ザルで水を切るのですが、この水切りが甘いとベチャベチャになりやすいです。
もち米の表面に残った水分や、ザルの底に溜まった水が余分な水分として加わってしまうからです。
プラスチック製のザルは水が切れにくいことがあるので、大きめの金属製の目の細かいザルで30分ほどしっかり水を切るのがおすすめです。
通常、臼と杵で餅つきをする際は、もち米を一晩水に浸すのが常識とされています。
しかし、多くのホームベーカリーでは、「浸水させないこと」を前提に水分量が設定されています。
そのため、良かれと思って浸水させたもち米をそのまま使うと、水分過多で失敗してしまいます。
もし浸水させたもち米を使いたい場合は、その分、加える水の量を減らす調整が必要になります。
例えば、もち米が280g(2合)で、水が180gで、合計460gになるレシピの場合を考えてみます。
もち米280gに50gの水を浸水させた時の重さは330gになります。
そこに180gの水を合わせると「330 + 180 = 510g」にもなってしまいますので、水が多い状態です。
この場合は、180gの水ではなくて、130gの水にすれば、「330 + 130 = 460g」となって、適正な水分量になるわけです。
浸水させたあとに、浸水させたもち米と水の合計質量をレシピ通りの重さにすれば良いんです。
これが、ベチャベチャになってしまう大きな理由です。
つきたてなのに硬いのはなぜ?
ベチャベチャではなく、出来上がりが硬くなってしまう場合があります。
この主な原因は、もち米に対する水分不足です。
考えられる理由の一つに、使用しているもち米自体の状態が挙げられます。
例えば、購入してから時間が経った古いもち米は、新米に比べて水分が少なく乾燥しています。
もち米の種類によっても違ってきます。
同じ水分量でも水を吸収しきれず、結果として硬い仕上がりになりがちです。
また、オート機能がない機種でこねる時間が短すぎると、十分に空気が含まれません。
密度が高い硬いお餅になりがちです。
さらに、ザルにあけて水切りをしてる場所が、エアコンがしっかり働いていたり風通しが良いときがあります。
そういった状態では、通常以上に乾燥がはげしくなります。
そういった水分が少ない状態でホームベーカリーで加熱すると、硬めの触感になりがちです。
ぶつぶつとした餅粒が残る悩み

つきあがったお餅を食べたときに、なめらかな食感の中に米粒のブツブツが残っているばあいがあります。
この「粒残り」の原因も、いくつか考えられます。
まず一つは、お餅が硬くなる原因と同様に、もち米が古いことが挙げられます。
乾燥した古いお米は水分を均一に吸収しにくいため、内部まで十分に加熱・加水されず、そのまま残ってしまう可能性があります。
ご飯でも同じように、古米の場合は、パサパサで固くなります。
なので、どうしても固くなってしまうときには、新米に変えたり、水分を多めにすると改善する傾向にあります。
そしてもう一つは、機械的な問題です。
ホームベーカリーの釜の底にある羽根がうまく回っていない場合、もち米が均一に混ざらず、加熱ムラやつきムラができて粒が残る原因になります。
お餅を作る前には、パンケースに羽根が正しくセットされているか、異物が挟まっていないかなどを確認する習慣をつけると良いでしょう。
また、何度も粒残りが起きるようであれば、一度羽根の回転部分などを掃除してみるのも一つの手かもしれません。
もち米を水に浸すのは本当に不要?
多くのホームベーカリーの取扱説明書には「もち米は洗って、水に浸さずに使う」と書かれています。
これは、機械が蒸す工程とつく工程を同時に、あるいは連続して行うため、浸水させていない状態を基準にプログラムが作られているからです。
だからこそ、取扱説明書に従うのが失敗しないための基本となります。
しかし、一方で「一晩浸水させた方が美味しいお餅になる」という声があるのも事実です。
これは、もち米の中心までしっかりと水分を行き渡らせることで、よりふっくらと、そして均一に熱が通るためです。
もし、あなたがより本格的な食感を求めて浸水を試してみたいのであれば、それは決して間違いではありません。
ただし、その場合は加える水の量を大幅に減らす必要があります。
そのためには、上述したように、質量ベースで考えましょう。
レシピに書かれてるもち米と水の重さを足しておいて、もち米に浸水させたあとにその重さを測って、合わせてレシピに書かれてる重さになるように水を計算すれば大丈夫です。
例えば、300gのもち米と200gの水がレシピだとします。足して500gですよね。
300gのもち米に思いっきり浸水させて400gになったら、水を「500g – 400g」で100gにすれば良いんです。
そうやって、水分を計算しながらホームベーカリーで何度か試してみれば、コツが分かってくるはずです。
失敗しない餅のつき方は水分量が鍵

ここまで見てきたように、お餅が硬くなるのも、柔らかすぎるのも、その多くは水分量の問題です。
なので、美味しいお餅を作るための「つき方」の鍵は、やはり水分量の微調整にあります。
というのも、夏と冬では室温が30℃くらい違うときがありますし、湿度も違います。
お米の種類も、住んでいる地域によって違ってきます。
教科書通りに、正確に重さを測って、ホームベーカリーに投入しても、微妙なズレはかならず出てきます。
なので、硬い、柔らかいと感じながら、水分量を少しずつ変えて何回も試していくことで、美味しいおもちを作れるようになるはずです。
少しずつとは、10mlから20mlほどで大丈夫です。
たったそれだけの違いで、驚くほど食感が変わることがあります。
ただし、変えるのは1ヶ所だけです。
いろいろ変えてしまうと何が良いのか悪いのかわからなくなってしまうので、水切り時間を一定にしたり、つく時間を一定にして、水分量だけを変えるようにしてみてください。
コツを押さえれば美味しいお餅に!
これまで見てきたように、ホームベーカリーでのお餅作りが美味しくないと感じるのは、いくつかの原因が重なっている場合が多いです。
しかし、裏を返せば、その原因と対策さえ知ってしまえば、誰でも美味しいお餅を作れるようになります。
ここまでのポイントを一度整理してみます。
- もち米選び
できるだけ収穫時期の新しい、美味しいもち米を選ぶ。 - 水切り
もち米を洗った後は、大きめの金属製のザルで30分間、しっかりと水を切る。 - 水分量
基本は取扱説明書通り。硬ければ少し増やし、柔らかければ少し減らす。
この3つの基本を押さえるだけで、あなたのお餅作りは劇的に変わるかもしれません。
最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、このひと手間が、お店で買うお餅とは比べ物にならない、つきたての格別な美味しさに繋がります。
ホームベーカリーの餅が美味しくない、を解決するヒント

- 餅つき機能ありとなしでの違いって?
- 餅メニューをつかったお餅のつくりかた【基本】
- 機能無しモデルでのお餅の作り方
- もち米2合で何個分くらい作れる?
- パナソニック製の特徴と便利な機能
- シロカ製の口コミと使いやすさ
- アイリスオーヤマ製の特徴と使い方
- 象印製の特徴とお餅の作り方
- ツインバードで作るおもち
- おもちメニューがないレコルトでのおもちづくり
- 後片付けやお手入れは大変?
- まとめ:ホームベーカリーの餅が美味しくないは誤解
餅つき機能ありとなしでの違いって?

ホームベーカリーを選ぶ際に、「餅つき機能」のあり・なしで迷う方もいらっしゃるかと思います。
この二つには、手軽さや仕上がりに違いがありますので、ご自身の使い方に合った方を選ぶことが大切です。
| 機能 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| あり | もち米と水を入れるだけで、蒸しからつきまで全自動で行う。 | ・手間が圧倒的に少ない ・初心者でも失敗しにくい ・コシのある餅が作りやすい | ・機能が多い分、価格が高めになる傾向 ・機種によっては作れるメニューが固定 |
| なし | パン生地などを「こねる」機能を利用して餅をつくる。 | ・比較的、手頃な価格の機種が多い ・パン作りに特化した機能が充実している場合も | ・もち米を別途蒸す(または炊く)手間がかかる ・こねる力が弱く、柔らかめの仕上がりになりやすい |
手軽に本格的なお餅を頻繁に楽しみたいのであれば、「機能あり」が断然おすすめです。
一方で、お餅作りはたまにで、主にパン作りを楽しみたい方や、少しでもコストを抑えたい方は、「機能なし」のモデルでも工夫次第で十分にお餅作りを楽しめます。
餅メニューをつかったお餅のつくりかた【基本】
ここからは、実際にホームベーカリーの「餅つきメニュー」を使った、基本的なお餅の作り方の流れをご紹介します。多くの機種で共通する手順ですので、全体のイメージを掴む参考にしてみてください。材料を入れてボタンを押すだけで、驚くほど手軽に本格的なつきたて餅が完成しますよ。
なぜなら、餅つき機能を搭載したホームベーカリーは、もち米を「蒸す」工程から、力強く「つく」工程までを、すべて全自動で最適に行ってくれるからです。私たちがすることは、ほんの少しの準備だけです。
必要なものはコチラです。
- もち米
- 水
- もちとり粉(なければ片栗粉)
- ホームベーカリー本体
- お餅を置くバットやトレイ
もち米と水の量は、取扱説明書や付属のレシピブックの量にしてください。
お餅を作るステップはコチラです。
- もち米を洗って水切り
- 材料をセット
- スタート
- 取り出して成形
ステップ1. もち米を洗って、しっかり水切り
まず、もち米を計量し、水がきれいになるまで優しくとぎます。
お米が割れないように、力を入れすぎないのがポイントです。
そして、ここが最初の重要な工程です。
とぎ終わったもち米を大きめの金属製ザルにあげ、約30分間、しっかりと水を切ります。
前述の通り、ここで余分な水分が残っていると、お餅が柔らかくなりすぎる原因になりますので、丁寧に水切りを行いましょう。
このとき、多くの機種の基本レシピでは「もち米を水に浸さない」と書かれています。
ステップ2. 材料をパンケースにセットする
お使いのホームベーカリーのパンケースに、「めん・もち羽根」が正しく取り付けられていることを確認します。
羽根をセットしたら、水切りしたもち米と、分量の水を入れます。
水の量は、お餅の仕上がりを左右する最も大切なポイントです。必ず正確に計量してください。
料理用の計量カップやデジタルスケールを使うと、より正確に計量できるのでおすすめです。
この一手間が、失敗を防ぐことに繋がります。
ステップ3. 「もち」メニューを選んでスタート
材料をセットしたパンケースを本体に戻し、ふたを閉めます。
あとは、メニューから「もち」や「もちつき」を選んで、スタートボタンを押すだけです。
機種にもよりますが、約1時間ほどでつきあがります。
あとは機械にお任せ。
この待っている間に、お餅を取り出すバットにもちとり粉を広げておくなど、準備をしておくとスムーズです。
ステップ4. つきあがり!熱いうちに取り出す
完成を知らせるブザーが鳴ったら、いよいよつきたてのお餅との対面です。
パンケースは非常に熱くなっているので、必ずミトンなどを使って取り出してください。
準備しておいたバットの上で、パンケースを逆さにするようにしてお餅を取り出します。
熱いので火傷には十分注意しながら、お好みの大きさにちぎったり、丸めたりして完成です。
必ず取扱説明書をご確認ください
この記事で紹介したのは、あくまで一般的な作り方の流れです。ホームベーカリーの機種によって、材料の分量、手順、所要時間などは異なります。お餅作りを始める前には、必ずお手持ちのホームベーカリーの取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従ってください。
機能無しモデルでのお餅の作り方

餅つき機能がないホームベーカリーでも、パン生地などを「こねる」機能を使ってお餅を作ることができます。
この場合、あらかじめもち米に熱を通しておく必要があります。
その方法としては2つあります。
最も手軽なのが、炊飯器の「おこわモード」などでもち米を炊いてしまう方法です。
手順はとてもシンプルです。
もち米を洗い、しっかりと浸水させてから、炊飯器の釜に入れて「おこわ」の水加減で炊飯するだけです。
もう一つは、蒸し器を使う方法です。
中華せいろや専用の蒸し鍋と、蒸し布を用意します。
蒸し器の下段にたっぷりの水を入れ、上段に蒸し布をしき、そこにしっかりと浸水させたもち米を広げます。
火加減は強めのまま約1時間蒸せば、出来上がりです。
どちらかの方法で出来上がった熱々のもち米をホームベーカリーの内釜に入れます。
パン生地やうどん生地のこねメニューで15分~30分ほどこねればおもちの出来上がりです。
熱いうちにバッドなどに取り出して、成形しましょう。
もち米2合で何個分くらい作れる?
ホームベーカリーでお餅を作る際、一度にどれくらいの量ができるのかは気になるところですよね。
作りすぎても余ってしまいますし、少なすぎても物足りません。
一般的に、もち米1合(約140g)からは、約240g〜250gのお餅(丸餅で6個)が出来上がると言われています。
そのため、多くの機種で最小単位となっているもち米2合(約280g)で作った場合、約480g〜500gのお餅(丸餅12個)が完成する計算になります。
もちろん、ご家庭で丸める大きさによって個数は変わりますが、4人家族で2〜3回に分けて食べるのにちょうど良いくらいの量、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
一度にたくさん作りたい場合は、3合や4合に対応した機種を選ぶと良いですね。
ご家族の人数や食べる頻度に合わせて、機種の容量を選ぶのがおすすめです。
パナソニック製の特徴と便利な機能

ホームベーカリーの分野で高い人気と信頼を誇るのがパナソニックです。
特に「ビストロ」シリーズなどは、パン作りの本格的な機能が注目されがちですが、お餅作りにおいても独自の技術が活かされています。
パナソニックSD-MDX4のもちレシピはコチラです。
| 材料 | 2合 | 3合 |
|---|---|---|
| もち米 | 280g | 420g |
| 水 | 180g | 260g |
| もちとり粉 | 適量 | 適量 |
もちとり粉は片栗粉や上新粉、コーンスターチなどです。(引用:パナソニック公式サイト)
作業手順(所要時間:1時間)
- もち米を洗う
- もち米は水に浸さない
- ザルで30分水切りする
- 内釜に入れる
- メニュー「36」でスタート
- ブザーが鳴ったら蓋を開ける
- スタート
- 出来上がり
シロカ製の口コミと使いやすさ
パナソニックと並んで人気なのがシロカのホームベーカリーです。
シロカ製品の最大の特徴は、手頃な価格帯でありながら、必要な機能を十分に備えているコストパフォーマンスの高さにあると言えるでしょう。
デザインもシンプルでコンパクトなモデルが多く、キッチンに置いても圧迫感が少ないのが嬉しいポイントです。
お餅作りに関しても、口コミを見ると「手軽に美味しいつきたて餅が楽しめる」といった肯定的な声が多く見られます。
シロカSB-2D151のもちレシピはコチラです。
| 材料 | 2合 | 3合 |
|---|---|---|
| もち米 | 280g | 420g |
| 水 | 220g | 320g |
| もちとり粉 | 適量 | 適量 |
もちとり粉は片栗粉や上新粉、コーンスターチなどです。(引用:シロカ公式サイト)
作業手順(所要時間:1時間25分)
- もち米を洗う
- もち米は水に浸さない
- ザルで30分水切りする
- 内釜に入れる
- メニュー「22」でスタート
- ブザーが鳴ったら取り出す
アイリスオーヤマ製の特徴と使い方

アイリスオーヤマのホームベーカリーにも「もちメニュー」があります。
アイリスオーヤマ製は、魅力的なコストパフォーマンスと、それを超える多機能性が特徴です。
特に「これからホームベーカリーを始めてみたい」と考えている方に、強くおすすめしたい選択肢の一つです。
なぜなら、比較的手に取りやすい価格でありながら、お餅作りはもちろん、食パンや米粉パン、ピザ生地、ジャム作りまで、一台で何役もこなしてくれるからです。
アイリスオーヤマIBM-020のもちレシピはコチラです。2合のみです。
| 材料 | 2合 |
|---|---|
| もち米 | 280g |
| 水 | 240g |
| もちとり粉 | 適量 |
もちとり粉は片栗粉や上新粉、コーンスターチなどです。(引用:アイリスオーヤマ公式サイト)
作業手順(所要時間:1時間15分)
- もち米を洗う
- もち米は水に浸さない
- ザルで30分水切りする
- 内釜に入れる
- メニュー「15」でスタート
- ブザーが鳴ったら取り出す
- 5~10分冷ましたら出来上がり
象印製の特徴とお餅の作り方
炊飯器や電気ポットでおなじみの象印ですが、ホームベーカリーの分野でも「パンくらぶ」シリーズとして、長年にわたり信頼性の高い製品を開発しています。
象印の製品づくりの根底にあるのは、炊飯技術で培われた「熱」を巧みにコントロールする技術です。
そのこだわりは、もちろんお餅作りにも活かされていて、「お餅の味やコシに、とことんこだわりたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
象印のホームベーカリー(パンくらぶ BB-ST10)は、パンの焼き上がりに徹底的にこだわっている点が特徴です。
例えば、パンケースの底に2つのヒーターを設置する「底面加熱ダブルヒーター」により、釜の温度を均一に保ち、焼きムラのない香ばしいパンを焼き上げるとされています。
このような加熱技術への強いこだわりが、お餅作りにおける「蒸し」の工程にも応用されており、もち米一粒ひと粒にムラなく熱を伝え、お米の甘みを引き出してくれます。
象印BB-ST10のK本のもちレシピはコチラです。
| 材料 | 2合 | 3合 |
|---|---|---|
| もち米 | 280g | 420g |
| 水 | 220g | 260g |
| もちとり粉 | 適量 | 適量 |
もちとり粉は片栗粉や上新粉、コーンスターチなどです。(引用:象印公式サイト)
象印のレシピブックには、基本のおもちを含め、5種類のもちメニューが載っています。(草もち、桜えびもち、ごまもち、もちグラタン)
作業手順(所要時間:1時間15分)
- もち米を洗う
- もち米は水に浸さない
- ザルで30分水切りする
- 内釜に入れる
- メニュー「25」でスタート
- ブザーが鳴ったら取り出す
- 5~10分冷ましたら出来上がり
ツインバードで作るおもち

「ものづくりの町」として世界的に知られる新潟県燕三条。
ツインバードは、この地に本社を構え、質実剛健で使いやすい家電を数多く生み出してきたメーカーです。
その製品哲学はホームベーカリーにも息づいており、日々の暮らしに寄り添う「ちょうど良さ」が多くのファンに支持されています。
ツインバードは、華美な装飾や機能よりも、実用性とシンプルさを重視する方に向いています。
ツインバードBM-EF38のもちレシピはコチラです。3合のみです。
| 材料 | 3合 |
|---|---|
| もち米 | 420g |
| 水 | 300~350g |
| もちとり粉 | 適量 |
もちとり粉は片栗粉や上新粉、コーンスターチなどです。(引用:ツインバード公式サイト)
作業手順(所要時間:1時間15分)
- もち米を洗う
- もち米は水に浸さない
- ザルで30分水切りする
- 内釜に入れる
- メニュー「17」でスタート
- ブザーが鳴ったら蓋を開ける
- スタートを押す
- 出来上がり
おもちメニューがないレコルトでのおもちづくり
「機能も大事だけど、やっぱり毎日目にするものだから、デザインにはこだわりたい」。
そんな方に絶大な人気を誇るのが、コンパクトでおしゃれな調理家電を数多く展開する日本のブランド、レコルト(recolte)です。
レコルトのホームベーカリーは、そのデザイン性の高さから「出しっぱなしにしておける」と評判です。
ただし、そのシンプルな設計思想から、多くのモデルではお餅専用のメニューが搭載されていません。
「デザインは理想的なのに、お餅が作れないなら…」と諦めるのは、まだ早いかもしれません。
ここでは、そんなレコルトのホームベーカリーを使って、少しの工夫でお餅を作る方法をご紹介します。
レコルトRBK-1では、基本的なもちレシピを使います。
| 材料 | 2合 |
|---|---|
| もち米 | 280g |
| 水 | 180g |
| もちとり粉 | 適量 |
もちとり粉は片栗粉や上新粉、コーンスターチなどです。
作業手順(所要時間:6時間)
- もち米を洗う
- もち米をしっかり浸水させる
- 蒸すか、おこわモードで炊く
- 内釜に入れる
- メニュー「9:こねる」を使う
- 15分でスタート
- 15分経ったら様子を見る
- 足りなければ延長してこねる
- 出来上がり
レコルトのホームベーカリーでは加熱ができないので、しっかり浸水させてから、蒸したり炊いたもち米をこねていきます。
なので、時間は1晩とか、通常のおもちづくりの時間がかかります。
後片付けやお手入れは大変?

おもち作りで気になるのが、後片付けの手間ですよね。
特に粘り気の強いお餅は、お手入れが大変そう、というイメージがあるかもしれません。
しかし、ここにも簡単なコツがあります。
一番のポイントは、おもちができたら、熱々のお餅をすぐに取り出して、パンケースに水を入れておくことです。
お餅が乾燥してカチカチに固まってしまうと、取り除くのが非常に大変になります。
しかし、つきあがりの熱と湿り気が残っているうちであれば、水に浸けておくだけで、ケースや羽根についたお餅がふやけて簡単に剥がれ落ちるようになります。
この習慣さえつけてしまえば、お餅作りの後片付けは、普段のパン作りの時とほとんど変わりません。
むしろ、バターなどを使わない分、楽だと感じる方もいるかもしれません。
まとめ:ホームベーカリーの餅が美味しくないは誤解

「ホームベーカリーの餅は美味しくない」という口コミについて、その原因や気をつけるコツをお伝えしてきました。
ここまで見てきたように、お餅が硬くなったり、逆に柔らかすぎたりする失敗の多くは、機械の性能が低いからではありません。
水分量の調整やもち米の鮮度、そして丁寧な水切りといった、ほんの少しのコツを知っているかどうかの違いです。
正しい知識と、ホームベーカリーの個性に合わせた少しの工夫さえあれば、誰でもお店で買うレベルの格別なつきたてのお餅を味わえます。
ホームベーカリーの餅が美味しくないというのは、単なる「誤解」です。
最後に、この記事でお伝えした大切なポイントを、改めて以下にまとめます。
このヒントが、あなたのホームベーカリーライフをより豊かにする一助となることを、心から願っています。
- ホームベーカリーの餅が美味しくないと感じる主な原因は水分量と米の状態
- 失敗の多くは「硬すぎる」「柔らかすぎる」「粒が残る」の3パターン
- お餅が硬くなるのは水分不足や古いもち米が原因のことが多い
- 柔らかすぎるのは水分過多や不十分な水切りが考えられる
- 粒が残るのは米の古さや機械の羽根の不調が影響している場合がある
- 多くのHBレシピはもち米を水に浸さない前提で水分量が設定されている
- 浸水させた米を使う場合は加える水の量を減らす調整が不可欠
- 固くならない餅のつき方の鍵は10ml単位での水分量の微調整
- 新鮮なもち米を選び、金属ザルで30分しっかり水切りするのが基本
- 餅つき機能なしのHBでも炊飯器とこね機能で代用可能
- もち米2合(約280g)で約480g、丸餅12個前後のお餅ができる
- パナソニック製は本格的な機能でなめらかな仕上がりが期待できる
- シロカ製は手頃な価格とシンプルさで初心者におすすめ
- 後片付けは、使用後すぐパンケースに水を入れるだけで格段に楽になる
- 正しい知識と少しのコツで、ホームベーカリーでも格別に美味しいお餅は作れる
ホームベーカリーの使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を守ってください。また、この記事で紹介した方法は、あくまで私個人の経験に基づくものです。アレルギーに関する情報や正確な製品仕様については、必ず各メーカーの公式サイトや専門機関にご確認いただきますよう、お願いいたします。