「電気ポットの寿命は?」
「変な臭いがしてきたけど大丈夫?」
「電気ポットの買い替えはいつ?」
電気ポットの調子が悪くて買い替えを考えてるあなたに、電気ポットの寿命とそのサイン、長持ちさせる方法などを紹介します。
電気ポットは家電製品の中でも使用頻度が高く、長期間使いがちな電気ポットです。
ただ、実は寿命の目安は5年程度といわれています。
中には10年、なかには20年近く使っている方もいますが、パッキンの劣化や空焚きが原因で故障するリスクが高まります。
例えば、電源が入らない、ランプがつかない、ロック解除できない、押してもお湯が出ない、沸かない、モーター音がしないといった症状が現れたら、寿命のサインかもしれません。
また、勝手に再沸騰したり、沸騰し続ける、臭いがするときもあります。
そのような状態の電気ポットでお湯を飲むと「体に悪い?」と不安になりがちです。
最後まで読んでもらえれば、今お使いの電気ポットの寿命がいつなのかわかって、長く安全に美味しいお湯を飲めるようになります。
- 電気ポットの寿命の目安とその根拠
- 故障の種類と具体的な症状や原因
- 寿命を延ばす正しい使い方と日常の手入れ方法
- 修理と買い替えの判断基準や処分方法
電気ポット寿命は何年が目安?
- 電気ポットの寿命は5年?10年?
- 電気ケトルと寿命の違い
- 故障の種類とそのサイン
- 電源が入らない時やランプがつかない時には?
- ロック解除できなかったり、お湯が出ない時
- 沸騰しない時
- 水が漏れている場合には
- お湯から臭いがする時~体に悪い?
- 勝手に再沸騰する時には?
- モーター音がしないとき
電気ポットの寿命は5年?10年?

電気ポットの寿命は一般的に5年とされています。
というのも、内閣府認定の公益社団法人「全国家庭電気製品公正取引協議会」で、補修用性能部品の保有期間が決められています。

左側の下に「電気ポット 5年」と書かれています。
これは、製造打切り後に、メーカーが部品を保有しておかないといけないのが5年だということです。
つまり、「この年数を過ぎて故障しても仕方ない=寿命」と同じ意味だと考えられるからです。
電気ケトルと寿命の違い

電気ポットと同じような家電に、電気ケトルがあります。
上記の表の中には電気ケトルはありませんが、部品保有期間は、電気ポットと同等の5年のメーカーが多いです。
ただ、電気ポットと電気ケトルは似て非なる家電です。
一見するとどちらもお湯を沸かす機器として同じ用途に見えますが、その使い方に大きな違いがあります。
電気ケトルは、比較的少量の水を短時間で沸騰させ、すぐに電源が自動的に切れる仕組みになっています。
これにより内部部品が高温にさらされる時間が短く、保温機能がないぶん劣化のスピードが緩やかです。
一方で、電気ポットはお湯を沸かすだけでなく、一定温度で長時間保温し続ける設計がされています。
これにより、内部は常に高温多湿の状態に置かれ、特にパッキンや電子基板、ヒーターなどの部品は長時間の高温により劣化が進みやすくなります。
そのため、電気ケトルは電気ポットよりも寿命がやや長くなる傾向があります。
故障の種類とそのサイン

電気ポットの故障にはいくつかの典型的な症状があります。
- 電源が入らない
- ランプがつかない
- ロック解除できない
- お湯が出ない
- 沸騰しない
- 水が漏れる
- お湯から異臭がする
- 勝手に再沸騰する
- モーター音がしない
こういった症状がでてきたら、寿命が近いと思ってもいいです。
というのも、これらのトラブルは単一の原因によるものが少ないです。
ポット内部に搭載されたモーターやヒーター、センサー、温度調整機能など、複数の部品が関与していることが多いです。
いわゆる経年劣化が進んでる状態で、一斉に不具合が生じることがあり、その先に寿命があると思われるからです。
また、複数の問題が重なって発生している場合や、何度修理しても不具合が再発する場合には、その電気ポットはすでに寿命を迎えていると判断して差し支えないです。
特に、5年以上使用しているのでしたら、故障してない部品の経年劣化も進んでいます。
無理に修理を繰り返すよりも買い替えたほうがコスパが高く、安全性も向上します
それぞれの故障の状態と、対応策、対処方法を具体的に見ていきます。
電源が入らない時やランプがつかない時には?

電気ポットの電源が入らなくなった場合、最初に確認すべきはコンセントやプラグの接続状態です。
ランプが一斉に消えたり、いつもついてる部分が消灯してるときも同じです。
たとえば、コンセントにしっかり差し込まれていなかったり、延長コードに不具合があると、電源が供給されません。
加えて、ブレーカーが落ちていないか、別の家電製品で同じ電源が使えるかなどを確認します。
それでも通電しない場合には、電気ポット内部の電子基板が故障している、あるいはヒューズが切れているといった内部的な問題が考えられます。
特に長年使っている電気ポットでは、部品が湿気や熱によって劣化しており、それが原因で電気が流れない状態になっていることが少なくありません。
また、安全上の理由でヒューズが切れている場合もあります。
こうした不具合を修理するには、製品を分解し、部品交換を行う必要がありますが、これは専門的な知識や工具が必要で、一般の方が行うのは無理です。
まずは、購入したお店に相談したり、メーカーの公式HPを探して、サポートをうけましょう。
その際には、保証期間内なのか、保証対象になるのかなどを確認することが大切です。
安全面からも、不具合が出た電気ポットを無理に使い続けることはおすすめできません。
内部の故障が悪化すると、発煙や漏電といった事故につながる危険もあります。
電源が入らないという症状は、電気ポットにとって重大なサインであるため、早めの対応を心がけることが大切です。
ロック解除できなかったり、お湯が出ない時

ロックボタンを押してもロック解除できないこともよくあります。
この場合は、スイッチがだめになったのか、内部の配線が切れたのか、制御マイコンが故障したのか、いろいろな原因があります。
ただ、電気ポットは防水のために密閉構造なので、中を開けて確かめたり修理するのは無理です。
給湯ボタンを押してもお湯が出ないときは、給湯ポンプの詰まりや内部モーターの不具合、電子回路の破損、パッキンの劣化などが発生している可能性があります。
モーター音がしていない時には、電子回路などの内部の破損で、修理に出さないと無理です。
モーター音がしてる時には、ミネラル分が付着してポンプを回せないという単純な原因も考えられますので、まずはクエン酸洗浄をお試しください。
数回試しても無理な場合は、ポンプ関連以外の故障だと考えられます。
電子回路がないエアーポット(押せば水圧で出るもの)は、パッキンやパイプが破損しています。
内部を確かめて、部品交換をすれば直ることがあります。
沸騰しない時
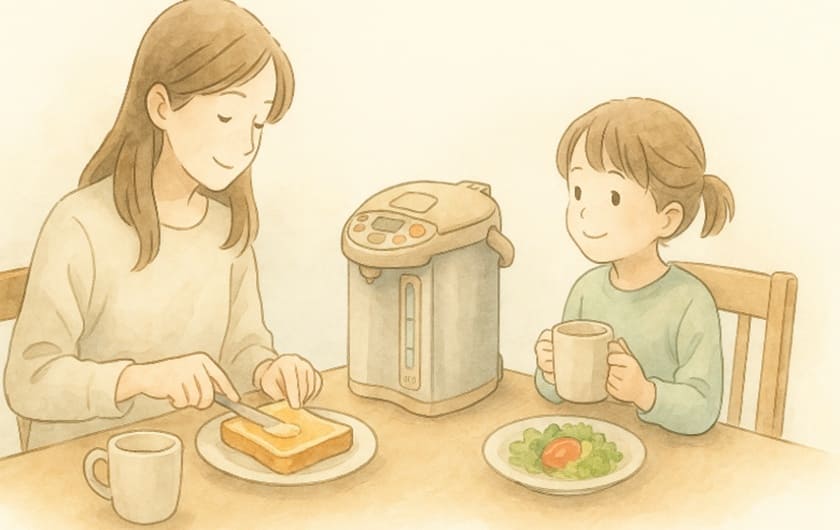
電気ポットに入れた水が沸騰しないという症状もあります。
モデルによっては省エネモードとかセーブコースなどがあって、沸騰しない設定の場合があります。
また、タイマー設定をしてる場合も、時間にならないと沸騰しません。
まずはそれを確認してみてください。
省エネモードなどが関係ない時には、制御マイコンの誤作動が考えられます。
内部に水がなかったり、過去に空焚きした履歴があると、保護回路が作動して安全のためにヒーターへの電力供給を遮断し、設定を変えてしまうことがあります。
多くの電気ポットには安全装置が備わっており、空焚きや異常加熱時には自動的に電源が切れるようになっているんです。
まずは、コンセントを抜いて30分ほど待ちましょう。リセットされて復活する可能性があります。
それでも改善されない場合は、ヒーターの断線や電子回路の不具合などが考えられますので、修理に出すか、買い替えるしかありません。
水が漏れている場合には

水やお湯が漏れてる時には、大きく分けて3つの原因があります。
- パッキンやフィルターの劣化
- 内部の中ビンがパッキンと密着してない
- 中ビンにヒビが入ってる、割れてる
まずはパッキンやフィルターが劣化してないかを確認します。
そのうえで、中ビンがぐらついていないかを確かめます。
確かめ方は、公式HPや取扱説明書に書かれてることが多いです。
また、中ビンが割れていないか、保温機能があるのかを確かめましょう。
保温機能があるのか確かめるには、電源を入れずに熱湯を入れて蓋をします。
しばらくたったあとに、側面の中央部から下を触ってみてください。
熱くなっていれば保温不良で、どこかしら割れています。熱くなければ保温機能は大丈夫です。
以上のことを確かめてみても、原因がわからない場合には、販売店や業者に修理見積もりをお願いしたほうが良いです。
お湯から臭いがする時~体に悪い?

お湯に異臭がする場合、その原因として最も多いのは、内部に使われている樹脂素材の経年劣化です。
次に多いのが、水道水に含まれるミネラル成分が時間とともに付着して起こる汚れの蓄積です。
こうした現象は、使用開始から数年経過した電気ポットに多く見られる傾向があります。
とくに保温機能を長時間使用しているお宅では、内部が常に高温多湿の状態にさらされるため、異臭の原因となる成分が発生しやすくなります。
異臭がする際には、次の作業をしてみてください。
- 1,2回、満水でお湯を沸かす
- 注ぎ口からお湯をすてる
- クエン酸洗浄をする
- お湯を注ぎ口から出す
おそらく、どの電気ポットにも、取扱説明書にクエン酸洗浄のやり方が書かれていると思います。
それを参考にしてやってみてください。
それでも臭いが取れない時には、買い替えたほうが気持ちがスッキリするはずです。
ただ、たとえ異臭がしても、それによってただちにあなたの体に深刻な影響を与えるような有害物質が出ているケースはまれです。
とはいえ、何らかの化学変化や劣化が進行している可能性があるので、そのまま使用を続けると、知らないうちに劣化成分を体内に取り込むことになります。
その結果、長期的な健康リスクを伴う可能性もあります。
また、異臭があるということは、ポット内部の清掃や部品交換が必要であるサインです。
そのままにして放って置かずに、何らかの対処をすることをおすすめします。
勝手に再沸騰する時には?

電気ポットが勝手に再沸騰を繰り返す場合、主に考えられる原因は温度センサーの故障や基板の異常です。
というのも、マイコン制御を使ってる電気ポットは、温度を適切に感知してヒーターのオン・オフを制御しています。
水を入れたから再沸騰するとか、勝手に再沸騰しない仕組みになってるというのはカン違いです。
例えば、85℃に設定していれば、何をしようが、84℃になれば必ず再沸騰します。
なので、取扱説明書を見て、もういちど温度設定をしてみることをおすすめします。
それでも再沸騰が繰り返されたり、沸騰してもとまらずにずっと沸騰し続ける場合は、内部の基盤が故障(ショート)したり破損しています。
丸洗いしたり、落としたり何処かにぶつけた記憶はないでしょうか。
そうした事をしてしまうと、底面やスイッチの部分から水が入ってしまい、その症状になりやすいようです。
モーター音がしないとき

スイッチを押してもモーター音がしないときがあります。
スイッチや電源、モーター関連の故障が考えられますが、モーターの羽根部分がカルシウムなどで固まってる場合もあります。
まずは、クエン酸洗浄などをして、内部をもう一度洗います。
そのうえで、内部の水を抜いて、本体を数回振ってみてください。
または、両方の手のひらで左右からトントンと軽く叩いて振動を与えてみてください。
凝固が原因の場合は、この作業でもう一度動き出す可能性があります。
それでもだめなら、修理か買い替えを検討してみてください。
電気ポットの寿命を延ばすには日頃のお手入れが重要
- 正しい使い方~使い始めが肝心
- やってはいけない使い方
- 毎日のお手入れ方法
- おかしいと思ったら、エラーコードと取扱説明書と公式HPを読む
- パッキン劣化に早めの対応を
- 空焚きは故障の原因になる?
- 修理代が高いなら買い替えも
- 処分方法と捨て方
- おすすめの電気ポット
正しい使い方~使い始めが肝心

電気ポットを長く安全に使い続けるには、最初の使い方が非常に重要です。
購入してすぐの使い始めの段階で、基本的な操作手順を正しく把握し、丁寧に取り扱うことで、電気ポットの寿命を大きく延ばせます。
まず、最初に行うべきことは「説明書をしっかり読む」ことです。
各メーカーごとに微妙な仕様の違いがあるため、あなたが使う電気ポットの特性や注意点を理解しておくことがトラブル防止につながります。
たとえば、初期洗浄の方法や水の入れ方、通電前の確認事項などが詳しく書かれています。
一度目を通すだけでもその後の使い方に大きな違いが出ます。
次に、水の入れすぎに注意することも基本です。満水線を超えると、沸騰時にお湯が吹きこぼれたり、内部部品に水がかかることで故障の原因になります。
また、常に清潔な水を使用し、古い水を長時間放置しないようにすることもポイントです。
内部に水垢や雑菌が蓄積すると、臭いの原因や衛生面のリスクが高まるばかりか、部品の劣化を早める可能性があります。
さらに、使用後の扱いも寿命に直結します。使用後は必ず電源を切り、プラグを抜く習慣をつけましょう。
これにより、無駄な通電を防ぎ、電気回路への負荷を軽減することができます。
ポット内にお湯を残したまま放置するのではなく、できるだけ早めにお湯を捨て、フタを短時間ですが少し開け、乾燥させるのもおすすめです。
特に注意したいのが、誤った操作を繰り返さないことです。
強くフタを閉めすぎたり、無理にボタンを押し続けることは、内部のスイッチやパッキンに過剰な負担を与え、早期の劣化を招く原因となります。
また、お湯を注ぐ際には、ロック機能や安全機能を正しく操作しないと、やけどなどの事故にもつながるため、日々の丁寧な取り扱いが求められます。
やってはいけない使い方

やってはいけない電気ポットの使い方もあります。
まず絶対に避けたいのが「空焚き」です。
水を入れないまま電源を入れると、ヒーター部分が過熱し、内部のセンサーや電子基板が故障する恐れがあります。
もちろん、ほとんどの電気ポットに空焚き防止機能がついてますが、使用前には必ず水が入っていることを確認する習慣をつけましょう。
また、「満水線を超えて水を入れる」のも危険です。
沸騰時にお湯が吹き出し、やけどや漏電のリスクが高まります。
加えて、蒸気口や注ぎ口が水に浸ってしまうと、センサーの誤作動を引き起こすこともあります。
ポットに記載されている目盛りは、ただの目安ではなく、安全使用の基準なのです。
次に、「ポットを濡れた手で触る」「水回りに置く」といった行動も感電や故障のリスクを高めるため避けましょう。
特に電源コードやスイッチ部分は水に弱く、濡れたままの状態で通電すると漏電の原因になります。
台所で使う場合は、設置場所にも気を配り、濡れた布巾や調理器具の近くに置かないようにすることが大切です。
「内部を研磨剤や硬いスポンジでこすってしまう」のもNGです。
内容器に傷がつくと、そこに汚れが入りやすくなり、結果としてにおいや雑菌の原因になります。
お手入れの際には、メーカーが推奨する洗浄剤や柔らかい布を使用するようにしましょう。
良くやってしまいがちですが、「蛇口から水を直接いれる」のもダメです。
水が電気ポットの内部にはいってしまう可能性があります。
もしも入ってしまったら、故障するリスクが高いです。
このような誤った使い方をしなければ、電気ポットをより安全に、そして長く使うことができます。
日々の何気ない使い方の中に潜むリスクを見直し、正しい使用法を身につけることが、結果的に電気ポットの寿命を延ばす最大の秘訣といえます。
毎日のお手入れ方法

電気ポットを清潔かつ安全に保ち、その寿命を延ばすためには、毎日の手入れが欠かせません。
特別な道具や洗剤を使わずとも、日々のちょっとした気配りを続けることで、性能を保ちつつ故障のリスクを減らすことができます。
まず、使用後には中に残ったお湯をなるべく早く捨てるようにしましょう。
長時間放置すると、水垢やミネラル分が内側に付着しやすくなり、内部部品の劣化を早める原因になります。
特に夏場は雑菌が繁殖しやすいため、使い終わったらお湯を捨て、短い時間、ふたを少し開けて乾燥させてから仕舞うことが推奨されます。
また、内容器の汚れが気になった場合は、やわらかいスポンジで軽くこすり洗いするだけで十分です。
絶対に金属製のタワシや研磨剤を使用してはいけません。
クエン酸を使った洗浄も効果的なので、月に1度くらいは内部を洗浄してください。水垢の予防と除去ができます。
外側も意外と汚れがちです。
キッチン周りでは油やホコリが付きやすいため、固く絞ったやわらかい布で外側の表面や取っ手、スイッチ部分を拭く習慣をつけましょう。
通電部に水が入らないよう、特に電源コードの根元や底面付近は慎重に拭く必要があります。
さらに、給湯口やふたの裏側も見落としがちな部分です。
ここには湯気や飛び散ったお湯が溜まりやすく、ヌメリやカビの原因にもなります。
布や綿棒などを使って、細かい部分まで丁寧に掃除をすることで、見た目の清潔感と機能性の両方を保つことができます。
このような日々のメンテナンスを継続することは、電気ポットの故障を未然に防ぎ、常に快適に使うための重要なポイントです。
手間に感じるかもしれませんが、習慣化すれば数分で終わります。
電気ポットを少しでも長く、安全に使い続けたければ、毎日の手入れをかかさないようにしましょう。
おかしいと思ったら、エラーコードと取扱説明書と公式HPを読む

電気ポットの調子がおかしいと感じたら、まずは落ち着いてエラーコードの表示を確認しましょう。
最近の電気ポットは、高機能なモデルであればあるほど、エラー発生時に画面やランプでエラーコードを表示してくれます。
エラーコードには、「センサー異常」「温度異常」「空焚き検知」「ポンプ不良」など、原因に応じた意味があります。
多くの場合はアルファベットと数字の組み合わせ(例:E03、H1など)で表示されます。
焦って操作ボタンを連打する前に、まずはそのコードの意味を知ることが重要です。
エラーコードの意味は、取扱説明書に書かれています。
取扱説明書には必ず、エラーコード一覧とその内容、対処法が明記されています。
「コードを確認して一度電源を切る」「水を入れ直す」「ポットを再起動する」など、ユーザー自身で解決できる対処法もあります。
説明書に沿って一つひとつ対応することで、回復する可能性もあります。
もし取扱説明書を紛失してしまった場合は、メーカーの公式ホームページにアクセスしましょう。
象印やタイガーといった主要メーカーでは、製品番号から該当する説明書のPDFを検索・閲覧できるようになっています。
また、Q&Aページや「故障かな?と思ったら」などのトラブル診断コンテンツも充実しているため、製品ごとの不具合の傾向や対策をチェックできます。
それでも原因が不明な場合や、エラーが消えない場合には、無理に使い続けず、販売店またはメーカーのサポート窓口へ連絡したほうが良いです。
エラーコードと使用状況を伝えることで、迅速かつ的確な対応をしてもらえます。
エラーが出たときには次の順番で対応することをおすすめします。
- エラーコードを控える
- 説明書・公式サイトで確認する
- それでもダメなら問い合わせる
パッキン劣化に早めの対応を

電気ポット内部に使用されているゴムパッキンは、日々の高温環境や水蒸気によって少しずつ劣化していく性質があります。
一般的には1年半から2年ほどで劣化が目立ち始めることが多く、定期的なチェックが欠かせません。
パッキンが劣化すると、お湯漏れや密閉機能の低下が起こり、内部の温度管理がうまくできなくなるだけでなく、外部に水分が漏れることで本体の腐食や感電リスクを招く可能性もあります。
このような症状を放置すると、本来の機能を果たせなくなるだけでなく、他の部品にも悪影響を与えるため、寿命を縮めることにつながります。
劣化が見られたら、早めの対処が重要です。
メーカーによっては交換用のゴムパッキンを安価に販売しており、専用の工具を使わなくてもあなた自身で取り替えられる電気ポットもあります。
特に注意して確認したいのは、パッキンの変色やひび割れ、硬化などの物理的な変化です。
ゴムが白く変色していたり、弾力が失われて硬くなっている場合は劣化が進んでいるサインです。
また、使用環境によっては寿命が短くなることもあるため、使用頻度が高い家庭では1年を過ぎたあたりから日常的に見るが理想的です。
パッキンは消耗部品なので、他の故障を未然に防ぐという意味でも、状態の確認と適切な時期での交換を習慣化された方が、電気ポットを長く安全に使えます。
空焚きは故障の原因になる?
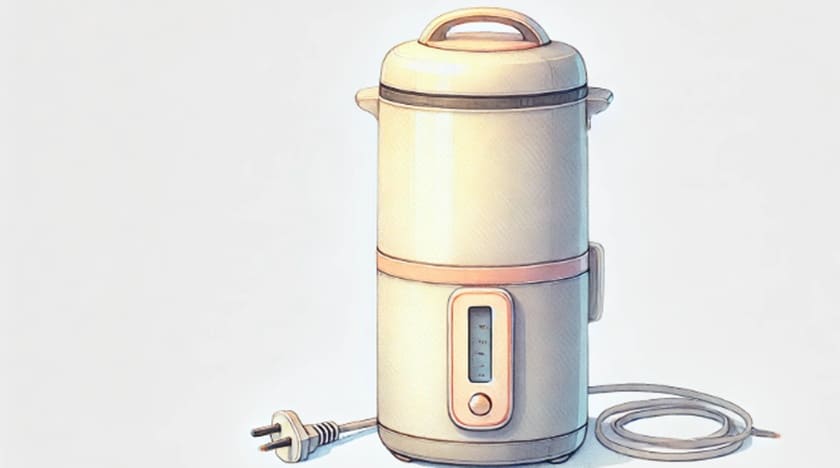
空焚きは電気ポットにとって非常に深刻なダメージを与える原因です。
内部ヒーターが水なしで通電されるのを繰り返すと、内容器のフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になります。
また、温度センサーが正しく機能しなくなったり、基板の損傷もおきたりするので、かならず内部の水を確認するのが大事です。
多くの電気ポットには、こうした事態を防ぐために空焚き防止機能が搭載されています。
この機能は、内部に水がない状態を検知すると自動的に加熱をストップする仕組みです。
ただし、保温のときには、たとえ内部の水がなくなっても自動で停止せず、保温し続けるモデルが多いです。
この場合、保温なので内部に支障は出ませんが、「沸かす」ボタンを押したり、蓋を開けたり、温度が下がると湯沸かしを再び開始します。
その際には空焚き防止機能が働いて通電ストップしますが、それを何度も繰り返すと、上記のように内容器に不具合がでてきてしまいます。
なので、使用前に必ず水が入っているかを目視で確認する習慣をつけることが非常に大切です。
朝の忙しい時間には無意識のうちに操作してしまいがちですが、毎回確認することで習慣化されるはずです。
電気ポットには空焚き防止機能がついていますが、空焚きは電気ポットの寿命を大きく縮めるだけでなく、火災や感電などの重大事故の原因にもなります。
些細な確認を怠らず、安全な使い方を日々意識することが、製品を長持ちさせるための基本であり、安心して使用し続けるための重要なポイントです。
修理代が高いなら買い替えも

電気ポットの修理費用は、症状やメーカー、交換が必要な部品の内容によって幅がありますが、一般的には数千円から高ければ1万円以上かかるケースもあります。
特に、温度センサーや電子基板、ヒーターなど主要な部品に不具合がある場合は、修理代が高額になりがちで、結果として新品の電気ポットを購入するのとあまり変わらない費用になることも少なくありません。
さらに注意すべき点として、製造終了から5年以上経過した製品は部品の供給期間が終了していることがあります。
このため、たとえ小さな故障であっても、古いモデルは部品が手に入らないので「修理できない」と言われる可能性もあります。
特に電気ポットを5年以上使用している場合、内部のパーツが複数同時に劣化している可能性も高く、仮に一部を修理しても他の箇所で新たなトラブルが発生することがあります。
こうした点を踏まえると、修理を繰り返すよりも、思い切って新しいモデルに買い替える方が現実的かつ経済的といえるでしょう。
また、最近の電気ポットは省エネ性能や操作性、デザイン、安全機能などが大きく進化しており、使い勝手も格段に向上しています。
節電タイマーや3段階保温設定、チャイルドロック、沸騰後の自動保温切替など、より便利で安心して使える機能が搭載されているため、新商品に買い替えによるメリットは非常に大きいです。
処分方法と捨て方

いらなくなった電気ポットは、自治体のルールをしっかり確認し、適切な方法で処分することが大切です。
自治体によって、不燃ごみ、可燃ごみ、粗大ごみ、小型家電などの処分の区分や出し方が異なります。
なので、まずはあなたが住んでるの地域のゴミ分別ルールを確認しましょう。
また、電気ポットは「小型家電リサイクル法」の対象製品です。
無料回収ボックスが設置されている公共施設や家電量販店などがあります。
こうしたリサイクルは資源の有効活用につながり、環境負荷の軽減にも貢献できます。
さらに、ビッグカメラでは新しい電気ポットを購入する際に古い製品の無料下取りサービスを行っています。
ヨドバシカメラとエディオンでは550円で、ヤマダ電機では指定段ボール詰め放題2,200円で回収サービスしています。
不用品が他にも多くある場合は、不用品回収業者にまとめて引き取ってもらう方法も便利です。
ただし、業者によって料金や回収条件が異なるため、複数の業者に見積もりを依頼して比較検討すると良いでしょう。
安全かつ適切に電気ポットを処分することで、不要な家電による事故のリスクを減らせるだけでなく、リサイクルを通じて環境保護にも貢献できます。
使い終わった製品に対しても、愛情や責任を持った対応を心がけたいものです。
おすすめの電気ポット

楽天市場やアマゾンなどで人気の電気ポットはこちらです。
- タイガー PDR-G221
- タイガー PIM-G220
- タイガー PIQ-G220
- 象印 CP-EA20
- 象印 CP-CA12
- 象印 CV-TE22
- 象印 CV-WB22
- パナソニック NC-BJ225
- パナソニック NC-SU224
まとめ:電気ポット寿命の目安と故障サイン
この記事のまとめです
- 電気ポットの寿命は一般的に約5年
- 寿命の根拠は部品の保有期間
- 電気ポットの保有期間は製造終了から5年
- 電気ケトルよりも寿命が短い傾向
- 故障のサインとして電源が入らない、ランプがつかないなどがある
- ロック解除や給湯ができない場合も故障の兆候
- 沸騰しない原因は省エネモードや制御マイコンの異常がある
- 水漏れはパッキン劣化や内部ビンの破損が原因となる
- お湯の異臭は内部樹脂や水垢の蓄積によることが多い
- 勝手に再沸騰する場合はセンサーや基板の異常が疑われる
- モーター音がしないときはカルシウム付着やモーター故障の可能性がある
- エラーコードの確認と取扱説明書の参照が初期対応として重要
- パッキンは1年半~2年を目安に劣化チェックが必要
- 空焚きは寿命を大きく縮めるため必ず水の有無を確認する
- 修理費が高額な場合や部品が手に入らない場合が多い
- 修理するよりも買い替えが現実的
- 正しい使い方と毎日の手入れが寿命を延ばす最大の秘訣







